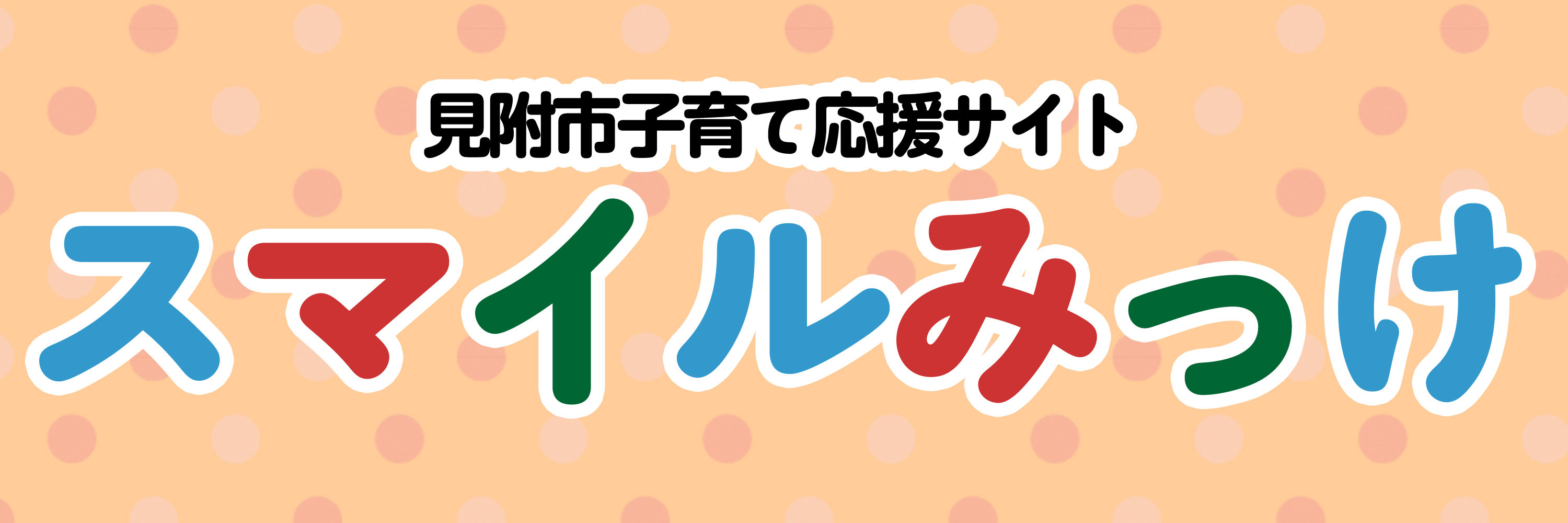本文
ふれあい懇談会(テーマ:教員対象 子育てについて)を開催しました
9月28日(木曜日)に、市立学校の教職員を対象としたふれあい懇談会を開催しました。「『子育てするならやっぱり見附』の推進に向けて」をテーマに、教職員の立場から感じる課題やご意見をお聞きしました。
開催日時
令和5年9月28日(木曜日)午後3時~4時50分
会場
見附市役所4階大会議室
一般参加者数
18名
稲田市長による説明資料
「暮らし満足No.のまち」を目指して~令和5年度見附市の取り組み~ [PDFファイル/3.76MB]
ふれあい懇談会で出た主なご意見・ご提案をご紹介します
- 起業家教育の推進が進められている。大切な理念だと理解はするが、学校現場は多忙な状況。新たな取り組みを行うときは、なくすものもセットで出してほしい。
- 起業家教育の推進について、教員は起業や商いの経験は薄い。市長からの冒頭のプレゼンで説明のあったソーシャルベンチャー事業の関係者、地域おこし協力隊員などを学校に呼ぶことも選択肢の一つだと感じた。
- スクールバスの課外活動での使用について、予約が他校との奪い合いとなる。また、運転手確保の問題から直前で断られる可能性があると聞いている。見学する施設は予約したもののバスが使用できない、というリスクがあると使いづらい。
- 午前のみの勤務となっている教育指導員を終日勤務としてもらえるとさらなる教員の負担軽減につながる。
- 教員の事務をサポートするスクールサポートスタッフの拡充をお願いしたい。教員に余裕ができ、子どもたちと対話する時間が生まれる。
- 「スクールアカウンタビリティ」に一般の市民の方が参加することが少なく、一堂に会する必要性があるのか疑問に感じている。学校だより等が地域に回覧されることで、学校の様子も伝わっている。アカウンタビリティ(=説明責任)としては、運動会や学習発表会といった機会もある。また、取り組みを動画にまとめてホームページに掲載し、いつでも見られるようにするというのも一つの形だと思う。
- 職場体験の依頼を各事業所に行うのが大変。市で職場体験を受け入れてくれる事業所をとりまとめてもらえるとありがたい。
- タブレット等の備品が不足している。
- 小規模校にとって指導助手の配置はとてもありがたい。
- 冒頭の市長からのプレゼンの中で、小規模校ではなく大きな学校に通わせたいという保護者の声を紹介されたが、地域の学校を大事にしたいという思いを持っている人もいる。オープンスクールで学区外から通う子もいる。地域の方々は学校の統合を非常に心配されている。
- 郊外の学校では年々児童数が減っているが、そんななかでも地域の環境に惹かれて移住してきた方もいる。そういった思いをお持ちの方は少なくないと思う。
- 駐車場が少ない。
- 和式トイレが多いので洋式化を望む。
- 児童数と教室数のアンマッチが生じている。
- 不安定な環境にある家庭にアプローチするタイミングや度合いの判断が教員では難しい。また、義務教育修了後の過ごし方に不安を抱える当事者や家庭も少なくない。サポート体制がより近くにあるとよいと思う。
- 見附市は部活動地域移行が進んでいてありがたいが、家庭での送迎の必要性が生じて申し込まなかったとの声もある。また、これまでなかった経済的な負担もかかってくることから、各種支援を望む。
- 学校と地域との連携のさらなる促進に向けて、ボランティアバンクや防災スクールなど、それぞれ別個で行われている市や地域と学校で連携した取り組みについて整理してもらえるとよい。企業から子どもたちのために協力してもらえること、あるいは学校や子どもたちにこういった活動を求めている、ということが可視化されるとありがたい。市の施策と学校の取り組みをうまく融合していけるとよいと思う。
- いまの子どもたちは柔軟な発想を持っている。子どもの声に耳を傾けることで、さまざまなアイディアが生まれてくると思う。
- 見附市は教育理念が一貫していると感じる。学校現場もそれに向かってみんなで頑張っていこうということで共有しやすい。
- こうして学校現場の声に耳を傾けてもらい、非常によい機会だと思った。これを機に子どもたちのより良い学びに向け、市と学校現場でさらに連携していければと思う。