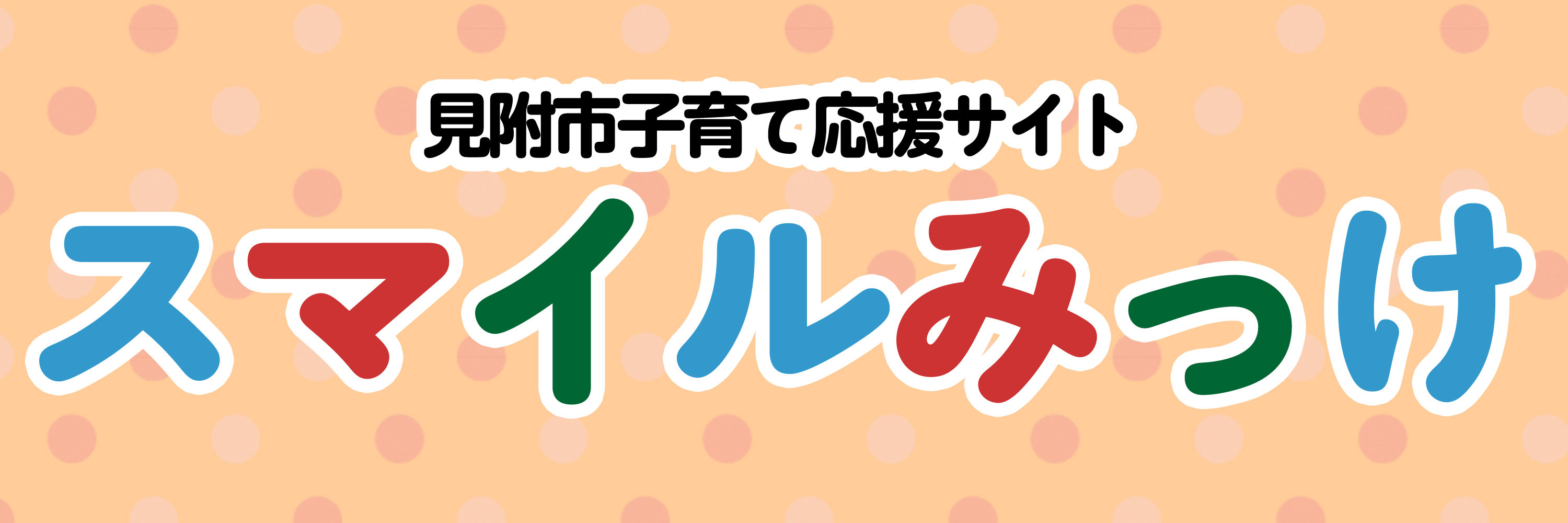本文
ふれあい懇談会(テーマ:障害福祉)を開催しました
5月30日(火曜日)に見附特別支援学校PTAの皆様を対象としたふれあい懇談会を開催しました。障害福祉をテーマに、市の施策などに対するご意見をお聞きしました。
開催日時
令和5年5月30日(火曜日)午前10時~12時25分
会場
見附市役所4階大会議室
一般参加者数
17名
稲田市長による説明資料
「暮らし満足No.1のまち」を目指して~令和5年度見附市の取り組み~[PDFファイル/3.47MB]
ふれあい懇談会で出た主なご意見・ご提案をご紹介します
- 近年放課後等デイサービスが充実しているので助かっている。フルタイムで働くことができ、家計を支えることができている。このように子どもを見てくれる場所が多くあるとありがたい。
- かつて学校生活において心無い言葉を浴び、悩んだことがあった。
- 障がいを持つ子の親は送迎に追われ、就業も簡単ではないと思う。
- 放課後等デイサービスをはじめ、福祉サービスが少しずつよくなっていることに感謝している。
- 障がい者施設で働いている。障がいのある子を育てる中で感じたことや同じように悩む保護者の声を聞き、新規事業(生活介護サービス)を立ち上げようと考えている。他市では福祉関連の新規事業を立ち上げるにあたって助成があると聞いたことがあり、見附市でも支援が受けられるとありがたい。
- 強度行動障害の困難事例となると、学校や放課後等デイサービスでも対応できる人材がなかなかおらず、家族が面倒を見ざるを得ない。プロフェッショナルな人材を育成してほしい。また、身体障害者手帳がないため、車いすを購入しようとすると全額負担となる。専門家の先生を呼ぶにもお金がかかるなど、経済的な問題が付いて回る。装具やコミュニケーションツール、車いす等の購入に補助を出してほしい。
- 医療的ケア児を抱えており、呼び出しも多いため仕事に就くのが難しい。今後、子が20歳になり特別児童扶養手当の受給対象から外れることを考えると生活に不安がある。
- 公営住宅に入居しているが、段差があるため子を背負って部屋に入っている。バリアフリー化を望む。
- 車いすでコミュニティバスに乗れないか問い合わせたところ、停留所での乗降対応は難しいとのことだった。日常生活で使えるよう、そういった現状があることを理解してほしい。
- 毎日子どもの世話に追われ、親は休む暇がない。市内にショートステイなど子を預けられる環境があれば、保護者の心身の負担も軽減される。
- 子の発語が止まらず家族が休まらない。一晩でも子を泊められる施設があるとありがたい。
- 子が就労実習に行っているが、卒業した後のことが心配。市や関係施設において、身体障がい者だけでなく精神障がい者の雇用ももっと考えてほしい。他市の特別養護老人ホームに勤めているが、そこでは精神障がいのある方を訓練などの段階的なフォローをしながら雇用している。
- 子が実習を行っているが、作業メニューが少ない。他市では製菓などもメニューにあり、食品系の福祉事業所での就労継続支援B型につなげられる。向き不向きもあるため、それぞれの子の特性に合った作業内容を見つけられよう、メニューに幅を持たせてほしい。
- 専門性の高い先生が少なく、配慮のない言葉を浴びることもあった。寄り添うように接してほしいし、成長を促すような指導をしてほしい。
- 日曜日に子を預かってもらえる施設を探したが、預け先がなかった。市外の施設に行かざるを得ない。
- 災害時に医療的ケア児を受け入れられる体制を望む。
- 見た目は障がいがあるように見えない子は周囲からの理解を得にくい。「軽度」とカテゴライズされるが、だからといって親の負担が軽いわけではないということをわかってほしい。
- 自分の周りも含め、使えるサービスがあることが意外と知られていない。相談に行くと「申請していただければ」と言われることも多いが、そもそも何を申請してよいかわからない。わかりやすい説明があるとありがたい。
- 市の職員にしても学校の先生にしても、言葉のチョイスに気を付け、配慮や寄り添う姿勢を見せて欲しい。
- 学校の時間に合わせて送り迎えをするとフルタイムで働くのが難しい。放課後は自分でお金を払ってファミリー・サポート・センターを利用するなりしてやりくりしなければならない。このあたりを福祉サービスで補ってもらえるとありがたい。
- 車いすを利用していると放課後等デイサービスに行くにも移動用の車を用意してもらう必要があり、移動手段の確保は大きな課題。
- 介護施設を利用した障がい者向けサービスを利用しているが、高齢化が進む中で、障がい者が受け入れてもらえなくなるのではないかという懸念がある。今後の展望や認識を聞きたい。
- 就労継続支援だけでなく、生活介護の利用が見込まれる子の卒業後の対応も考えてほしい。
- 見た目ではわかりづらい「グレーゾーン」の子に対する社会からの寛大なまなざしや市民全体での理解の醸成を望む。
- 放課後等デイサービスに専門性のあるスタッフを配置し、安全を確保できる体制にしてもらいたい。