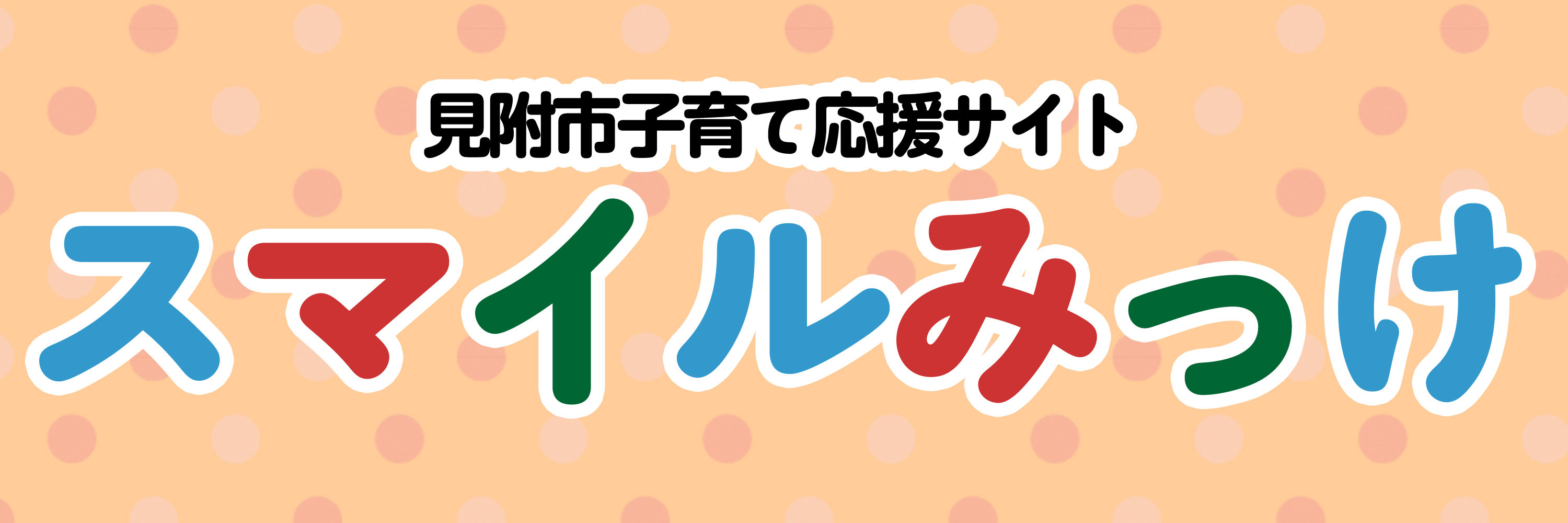本文
令和6年度 施政方針
本日ここに、令和6年3月市議会定例会が開催されるにあたり、市政運営に臨む私の姿勢と所信の一端を申し上げますとともに、令和6年度当初予算案の重点施策など、その概要をご説明申し上げます。
今年の元日に発生した令和6年能登半島地震は、石川県をはじめ県内にも甚大な被害をもたらしました。被災された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
市内では大きな被害がなかった一方、被災地では今もなお多くの方々が避難生活を続けています。見附市ではこれまで、被災地から要望のあった支援物資などの提供、救急隊員や水道等技術職員、トイレトレーラー、災害支援ボランティアの派遣などを行っています。今後も支援を続けていくとともに、今回の地震を教訓として「いつ起こるか分からない災害」に対する備えをより一層強化していく所存です。
また、昨年は新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられ、コロナ禍から本格的に動き出した年でした。市内でも各種催し物が通常開催され、地域コミュニティや市民団体によるイベントを含めて、まちに活気が戻りつつあります。
一方で、市内交通機関の運転手をはじめとする人手不足や、物価高騰などが市民生活や地域経済へ影響を及ぼしており、こうした情勢をしっかり見極めて対応していく必要があると感じています。また全国的な人口減少・少子高齢化は、地方でその動向が顕著であり、見附市も例外ではありません。しかしながら、「新潟県のど真ん中」「交通の便が良い」「産業立地が進んでいる」「コンパクトなまち」などの見附市の特性を活かせば、人口減少を少しでも抑制し、将来に向かって持続可能で元気なまちにしていけると確信しています。
その鍵となるのは、次世代を担う若者や子育て世代です。彼らが「住み続けたい」「戻ってきたい」「新たに住みたい」と思ってもらえる必要があり、若者たちが稼げる、暮らせる、子育てできる環境のさらなる充実を進めます。特に子育て環境については、昨年市内で小児科医院やプレイラボがオープンするとともに、中学生以下のコミバス無料化、子育てしやすい企業の職場づくり、子育てママ健幸スマイルスタジオなど様々な取り組みがスタートしました。また、年によって変動のあるデータですが、令和5年9月までの1年間の人口千人当たりの出生率が県内20市中でナンバー1にもなりました。さらに、今議会に「こども・子育てどまんなか条例案」を提出、今年4月からは放課後児童クラブや民間による教育・保育施設などの充実がより一層進みます。また長岡市内でありますが、見附市に近い位置に産婦人科医院の整備が進められていると聞いております。こういった子育て環境のみならず経済面や交通など若者が暮らせる環境の一層の充実を図るとともに、見附の魅力の戦略的かつ効果的な発信や見附ファンの拡大と交流などを進め、若者の見附への移住定住の促進もしっかりと進めてまいります。
また、子育て世代のみならず、高齢者や障がい者など、あらゆる世代や境遇の市民の皆様が安心して健幸に暮らせるまちづくりも進める必要があります。今年は、元日から能登半島地震が発生したことに加え7.13水害や中越地震発生から20年の節目を迎え、災害への備えなどの安全対策の強化を進めるなど、地域コミュニティや市民団体などとも力を合わせ、誰一人取り残さないまちを目指してまいります。
一方で、見附市の財政は、今は危機的な状況ではありませんが、将来を見据えると楽観視できる状況ではありません。様々な取り組みに積極果敢にチャレンジしていく余力を確保するために、収入確保と合わせ、これまでの取り組みも躊躇なく見直すことが必要不可欠です。未来を見据えて優先順位を考えながら、市民の皆様への説明責任を果たしつつ進めてまいります。
以上のような方針のもと、職員一丸となって議論を重ね、令和6年度予算案をまとめました。
その新年度一般会計予算は、国の施策として実施する定額減税に関連する事業費5億1,900万円の影響等もあり、総額189億1,000万円となりました。これは前年度に比べて14億9,000万円、8.6%の増となります。また、4特別会計の合計は82億500万円となり、前年度比4億700万円、4.7%の減となりました。3公営企業会計の合計は84億5,100万円となり、前年度比1億3,200万円、1.6%の増となりました。それでは、新年度予算につきまして、「暮らし満足No.1のまち」実現に向けて重要となる7つの考え方をもとにご説明申し上げます。
1つ目は、『まちと産業を元気にする』です。
見附への移住・定住と結婚の促進としては、移住の取組みに関する知見と実績がある民間事業者と新たに連携し、見附居住の魅力を効果的に届けるための戦略づくりと情報発信を行う移住定住プロモーション事業を展開するとともに、移住を検討する方が見附の生活環境を体験できるようお試し移住拠点を整備します。また県のUIターンフェアへの出展に加え、新たに中越圏近隣市と連携したセミナーを開催し、若者子育て世代を中心に見附への移住定住を選んでもらえるよう戦略的に展開してまいります。
加えて、新婚世帯に対しては、見附での新生活のスタートアップ経費に対する支援の規模を拡大するほか、結婚したい人を応援するため、県のマッチングサービス「ハートマッチにいがた」への入会登録料への補助を新たに行います。
交流人口や関係人口の拡大促進としては、これまで比較的緩いつながりを指向してきた「見附さぽーた」について、特に若年層を対象とした交流会を新たに開催し、より強い関係を築いていきます。また地域力創造事業で地域活性化に取り組んでいた地域おこし協力隊には、令和5年度の経験や人脈を活かし、移住定住の促進や関係人口の拡大に向けたPR活動などの取組みを行ってもらいます。
交流人口の拡大に向けては、スポーツツーリズムとインバウンドなどに注目します。スポーツでは、これまでも行われてきた市内合宿など訪問者へのおもてなしを強化するとともに、徐々に発展してきた女子野球大会を見附名物の1つにするべく盛り上げて、地域経済の活性化や関係人口拡大へとつなげます。また外国人訪問者数増加率全国5位と報道されたことを地域経済の活性化にいかせるよう、令和5年度に作成した観光ガイドブックの英語翻訳版を作成するほか、海外からの技能実習生とも連携して見附の魅力発信などに取り組みます。また、手軽で人気のアクティビティとして注目される電動キックボードを導入し、道の駅パティオにいがたの魅力アップと今町等周辺地域への散策誘導につなげます。
新たにチャレンジする産業界支援と交流の強化に関し、令和5年度にソーシャルベンチャー事業の最優先課題として取り組んだふるさと納税の寄附額増加については、目標に届かなかった一方で返礼品数の増加や新規返礼品の開発など一定の成果もありました。これらの課題や成果をふまえて体制を見直し、地域活性化起業人2名を国の制度を活用して引き続き受け入れ、豊富な知識と経験や人脈を活かしながら、事業者への事業拡大支援とふるさと納税返礼品の新規開発を進めます。加えて、ふるさと納税に関する専門的なノウハウと実績を有する事業者に業務委託し、地域活性化起業人との連携も図りながら寄附額の増加を図ります。
農商工連携に向けては、異業種間の交流会を引き続き開催し、地域活性化起業人にも関わってもらいながら、相互の関係づくりと事業連携を促進します。
見附で働く仕組みの構築と強化としては、事業者の人材確保につながるよう市内事業者のみが参加する就職ガイダンスを見附商工会と連携して開催します。また農業に関しては、猛暑渇水にともなう米の等級低下等による減収対策として収入保険加入を促進する保険料支援を継続するほか、農家が加入できる農作業労働力確保支援アプリの利用料を支援し農繁期の人手不足解消とともに将来の担い手確保へのきっかけづくりを進めます。
若者・子育て世帯などを呼び込む交通・住宅環境の確保としては、運行台数が減少しているタクシーや将来の減便が懸念されるバスの運転手を確保するため、新たに、公共交通事業者に対して第二種免許取得への支援を行います。夜間やコミュニティバスが運行していない地域などにおける公共交通のあり方については、この支援の成果や年末年始に社会実験として実施したジャンボタクシーの夜間運行結果、自治体研究会に参加を決めたライドシェアの議論なども踏まえ、タクシー事業者や地域コミュニティ等と議論を進めるほか、地域公共交通計画の中間見直しにあわせた最適化を検討してまいります。
見附駅周辺開発については、令和6年度開設予定の駐輪場2階の交流施設の運営や周辺地域の賑わいづくりについて地域おこし協力隊を活用しながら官民連携で推進するほか、東西自由通路と駅舎に関して現在進めている検証を踏まえて基本構想やイメージを改めて整理します。
ウエルネスタウンの販売や利活用の促進に向けては、専門的な知見を有する民間力を活用するため地域活性化起業人を採用して戦略の再構築を進めます。
2つ目は、『子育て・教育』についてです。
働きながら育てられる環境の整備については、引き続き強力に進めます。子育て中の方などフルタイム勤務や自宅以外での勤務が困難な方に対し、テレワークによる柔軟で多様な働き方ができるよう支援するほか、子育てしやすい職場づくりに努める企業に対し、財政支援や子育て情報の提供などを継続的に進めます。また企業の取り組みへの評価を市が発注する事業の入札制度に反映できないか検討するほか、市内企業を先導できる存在となれるよう見附市役所における働きながら子どもを育てられる環境改革を令和6年度より順次進めます。
また令和6年度は、首都圏で実績のある団体が運営する「見附どろんこ保育園」が新たに開園するほか、見附みどりこども園がリニューアルされます。市として私立保育園やこども園の運営を支援するとともに、充実した環境を市内外へ積極的に発信していきます。
続いて子どもの居場所・遊び場・活動の充実についてです。利用希望者数が増えている放課後児童クラブについては、葛巻地区と新潟地区においてそれぞれ閉園する保育園や既存園舎を活用することで受け入れ体制を確保します。中学生のスポーツ・文化活動の選択肢確保については、来年度体育系部活動の受け入れ先を5種目に拡大するほか、文化系部活動についても運営や指導を行う受け入れ先団体を検討して活動の委託を進めるとともに、現在部活動で行われている種目以外の選択もできるよう検討を進めてまいります。また、大平森林公園にドッグランや足漕ぎボートなどを新たに整備する他、チャプチャプランドやみつけイングリッシュガーデンの遊具修繕なども実施し、親子でもっと出かけたくなる公園整備を進めてまいります。
子育て・出産に対する負担軽減に向けては、1・2歳児の第3子以降の保育料の全額公費負担について、第1子・第2子とも保育園児の場合に限られていたのを18歳以下である場合まで対象を拡大し、多子世帯の経済的負担をより一層軽減します。また学校町子育て支援センターにおける一時預かりについて、これまで利用できなかった保育園児も利用できるよう対象を拡大するほか、国が市町村と連携して試行的に実施する「誰でも通園制度」について市内の私立保育園や認定こども園において実施できるよう支援します。さらに、これまで自己負担だった1か月児健康診査について公費助成を行います。
取り残されることなく子どもたちが育つ環境づくりとしては、不登校の児童生徒への対応を強化するため、既存のすこやかルームに加えて公民館と併設するふるさとセンターに「ふるさと教育支援センター」を設置して、子どもたちの社会的自立に向けて多様な学びを得られる環境づくりを地域総がかりで行っていきます。また児童虐待対応を行う必要な資格を有する子ども家庭支援員を新たにこども家庭センターに配置します。
見附で育てたくなる教育活動の充実に向けては、起業家精神や起業家的資質能力と言われる他者と協働しながら新しい価値を創造する力を育成するため、市内の小・中・特別支援学校において、職場体験や起業体験、アイデアコンテストなどによる「みつけJobチャレ教育」を官民学が連携して推進していきます。これにより将来見附に戻って起業する子どもたちが少しでも出てくることも期待しています。また、ベトナムダナン市への中学生派遣事業を再開するほか、中学1年生のみとしていた英語検定支援対象を中学3年生に拡大します。
子どもたちが安心できる環境に向けては、名木野小学校において大規模となる長寿命化改修工事を、見附小学校においては小規模な部位改修工事を実施します。また近年の猛暑などの影響も踏まえ、公立保育園3園において園児が安心かつ快適に過ごせるよう遊戯室へのエアコンや電子錠を整備します。
将来に向けた子育て・教育のあり方としては、子育てサービスのさらなる充実を図るため、今議会に提案した「こども・子育てどまんなか条例案」を踏まえつつ、既存の「子ども・子育て支援事業計画」に「若者育成」と「子どもの貧困の課題解決」の視点も加えた「こども計画」を新たに策定します。また、5年後10年後の見附市の教育環境について幅広く市民の声を聞いた「タウンミーティング」の結果や総合教育会議での議論を踏まえ「公立小中学校の適正規模などのあり方を検討する市立学校配置等検討委員会」を設置することとなりました。未来を担う子どもたちの教育環境を重視しながら、委員会に参加する学識経験者や市民の皆様とともに一定の方向性を導きだしてまいります。
3つ目は、『健幸』についてです。
地域医療体制の充実については、これまで取り組んだ結果、昨年4月に新町にて3医院が開業しました。引き続き、現在または将来不足する診療科目を対象に支援制度を継続し、関係機関への働きかけを積極的に行っていきます。見附市立病院における医師確保に向けては、1月に獨協医科大学との間で医学生の地域枠の新設に関する協定を結んだところであり、卒業後5年間市立病院で勤務してもらうことなどを条件に返済が免除される修学資金の貸与を行います。地域枠学生には、将来を見据えて見附市に親しみを持ってもらえるようサポートしてまいります。
また、人工透析通院者のニーズに応えるため、通院にかかる自家用車や福祉タクシー利用料金の助成額を増額するとともに、常時車椅子を利用している方にはタクシー券の配布冊数を上乗せします。
健康増進施策の充実としては、健幸ポイント事業の対象年齢をこれまでの30歳から18歳に引き下げ、新たにスマートフォンのアプリでも参加できる仕組みを導入するなど、より多くの市民の健康増進や運動習慣の定着を図ります。
誰も取り残されない社会の実現に向けては、高齢、障がい、子ども、生活困窮といった枠組みを超えて一体的な相談支援を行う「重層的支援体制整備事業」について、令和7年度の本格実施に向けて、連携や支援体制の充実を図ります。
また、障がいを理由としたいかなる差別も許されないことを市民の皆様と共有し、それぞれの立場で差別の解消に向けて主体的な取り組みや共生社会の実現を目指すための条例について、令和6年度中の制定を目指して検討に着手するほか、障がい者が活躍できる就労先の拡充に向けた企業向けセミナーを開催します。
また、補聴器購入助成に対する対象年齢の上限を撤廃して75歳以上の高齢者の外出や活動を後押しするほか、パートナーシップ制度については、県の動きを踏まえて積極的な対応を検討していきます。
環境問題への取り組みとしては、令和5年度に引き続き見附駅東口駅前広場の融雪に地中熱を活用するほか、太陽光発電システム補助金の対象を個人だけでなく事業者にも拡大し、脱炭素を推進します。また、将来の容量不足を見据えた新しい最終処分場の建設に向けて基本設計を行います。
4つ目は、『安心安全』についてです。
災害に備える体制の整備は、地域コミュニティや市職員退職者にも協力を得るなど避難所開設や対応などに関する体制強化を図ります。6月23日に予定している来年度の総合防災訓練では、町内ごとの住民避難体制の確認を行うほか、外国人避難や地域コミュニティとの連携強化についても取り組む予定です。
地震時の対応については、能登半島地震における市内や被災地での対応状況を踏まえつつ、初動や連絡体制、避難所対応などについて検討と見直しを進めます。
水害については、7.13水害から20年目の節目の年になることを踏まえ、災害から得られた教訓と防災技術を後世に伝えて安全・安心な地域づくりに活かすため、国・県・他市町村と共同でシンポジウムを開催します。
さらに災害時に自ら避難することが困難な要支援者の避難支援マップ等の個別避難計画について令和6年度中に作成を概ね完了させるほか、県が新たに作成した浸水想定区域図を、既存のハザードマップの追加情報として作製し全戸配布します。
地震等に備えた施設やインフラの安全対策強化については、まず中央公民館の吊り天井の耐震改修等に伴う設計に着手します。木造住宅については、耐震診断が進んだことや今般の能登半島地震での現地被害を踏まえ、耐震設計および耐震改修に関わる補助枠を拡大し、耐震化を促進していく他、建て替えや住み替えを促すための既存住宅の除却も新たに支援対象とします。下水道については終末処理場の耐震強化や管路等の老朽化更新を強化します。市役所庁舎については、外壁タイルの落下を防止するため、外壁修繕および屋上防水工事を進めます。
水害対策施設の整備としては、貝喰川流域の浸水被害を軽減する県の大規模改修事業の早期完了に向け、県の委託事業である埋蔵文化財の発掘調査の規模を拡大して改修事業の加速化を後押しするほか、雨水渠の整備を推進します。
持続可能な雪害対策としては、持続可能な除雪体制の確立に向けて、除雪事業に対する除雪機械の固定費支援を拡充するほか、地域による消雪設備の持続的管理に向け、設備支援対象に安価な手法を加えて拡充します。
消防力の維持充実としては、119番通報者のスマートフォンを利用し、通報者と通信指令室の間で映像を送受信できる「Live119システム」を新たに導入するほか、老朽化が進んでいる救急車などの車両更新を図ります。
5つ目は『市民の皆様に寄り添う』です。
まちづくりの主役である市民の皆様の声を聞くことは、「暮らし満足No.1のまち」を目指す上で欠かせません。引き続き月1回ペースを目途に「ふれあい懇談会」を開催するとともに、私も職員も様々な機会をとらえて市民の皆様と交流し、課題や市民ニーズの把握に努めてまいります。また、広く市民の声を集約し、今後の施策や次期総合計画に反映させるため、市民アンケートを実施します。
ICTの活用については、入札参加者の利便性の向上と透明性確保を目的に電子入札の導入を図るとともに、議場設備の改修や戸籍情報システム移行などを実施します。今後、今年度開始したLINEやリニューアルしたHPの有効活用、配布物の電子化など市民の皆様への発信情報、マイナンバーカードの活用、市役所内の業務効率化などの分野において、更なるデジタル化を検討してまいります。
6つ目は、『あらゆる力を結集する』です。
時代のニーズにあった地域コミュニティの活性化としては、市内11の地域コミュニティ組織が自由な発想で行う、地域住民の関係づくりや地域課題の解決を図る自主的な活動に対する地域ふるさとづくり活動交付金について、コミュニティ提案型予算であるチャレンジ枠の拡充などの見直しを行ってさらなる活性化を促進するとともに、地域コミュニティを核とした嘱託員、民生児童委員、公民館等との連携強化や事務の効率化についても検討を進めます。
市民活動への支援としては、現在検討を進めている旧寺師医院の活用を含めて市民活動が持続可能となるよう、体制づくりを含めた支援のありかたを検討していきます。
職員力の強化と活用に関し、今年度は、人口減少対策をはじめとする今後の市として行うべき取り組みについて、改めて職員に提案を求めました。職員から合計16件の提案があり、4件を事業化の検討対象として評価されています。来年度予算案に計上した道の駅への電動キックボードの導入はその1つです。同様に職員提案の1つであった「見附未来WG」という政策検討チームを発足したいと考えています。これにより、職員による考える力を強化するとともにボトムアップによる施策づくりをより一層進めて参ります。また、同規模の他の自治体と交流して学びあう機会を設けるなど職員力の強化育成に努めてまいります。
7つ目は、『行財政検証』についてです。
大型事業としては、見附駅自由通路整備事業、ウエルネスタウンの販売戦略の見直しに加え、地域力創造事業について、これまでの成果を勘案しアドバイザーとの契約を継続しないこととするとともに成果が認められる点は、そのままいかす方向で体制の見直しを図ります。また、農業集落排水を公共下水道に統合し汚水処理施設の維持管理の効率化を図るほか、下水道の維持管理について職員数の減少や施設の老朽化、使用料収入の減少などの課題に対応するため、地域の民間活力を用いて効率的に施設の維持管理・更新を行う「ウォーターPPP」の導入可能性調査を実施します。
既存事業については、地域コミュニティに交付する地域ふるさとづくり活動交付金のうち、敬老会に使途限定する補助を廃止する一方で、各コミュニティの提案に基づいて配分する「チャレンジ枠」を増額するなど、地域の課題解決に向けて柔軟に使える仕組みに見直しました。また、政策意義や必要性の低下などの観点から、通信環境整備補助や嘱託員へのファックス貸与、生涯現役促進地域連携事業を廃止します。健康運動教室や健幸ポイント事業、紙おむつ券給付事業などについては、国補助の動向なども踏まえて効率的な実施方法に見直すなど事業費の低減を図ります。
収入増加に向けては、ふるさと納税の寄附額について令和5年度は残念ながら増加が見込めない状況ですが、体制の徹底強化により令和5年度と同じ1.5億円の目標を掲げます。企業版ふるさと納税については、見附にゆかりある企業への働きかけを進めた結果、令和5年度は対前年度10倍以上に寄附額が増加、イングリッシュガーデン協力金や使用料収入についても料金などを見直した結果、対前年度比で約3倍に増加しました。これらの取り組みをさらに強化するとともに、経済活性化や移住促進などの取り組みと併せて財源確保を図ってまいります。
なお、行財政の見直しについては、まだ手始めの段階と認識しています。事業や補助制度に加え、市の直営及び指定管理施設そのものや、運営のありかたについて、徹底的な見直しが必要になるものと考えています。民間に頼れることは民間で、地域に頼れることは地域で、外部の力が必要なことはその力を借りて、他のどこにも頼れないことは公共で、場合により統廃合も含めた聖域のない議論も必要です。市の現在の総合計画や総合戦略が令和7年度までで終了することから次期計画の検討着手などとあわせ、施設の見直しを検討する体制もしっかり考えてまいります。
以上、「暮らし満足No.1のまち」実現に向けて重要となる7つの考え方を中心に、令和6年度、見附市が取り組もうと考える主な施策について、その概要を申し上げました。
昭和29年3月31日、当時の1町3村が合併して見附市は、今年で市制70周年の節目を迎えます。記録的な水害・地震・雪害など幾多の苦難を乗り越え、先人の皆様が積み上げてきた70年の歴史があるからこそ、今の見附市があり、今の私たちがあります。ただ、愛すべき「ふるさと見附」を輝かしい未来へとつなげるためには、先人の皆様から受け継いできたことに敬意を表しつつも、時代に即した新しいニーズや手法を取り入れ、未来志向をもって持続可能なまちづくりに積極的に取り組んでいかなくてはなりません。
究極の目標としている「暮らし満足No.1と思えるまち」の実現に向けて、引き続き市民の皆様の声をしっかりと聞き、新しい感覚をとらえる学べる場に市職員とともに数多く出向いて知識の共有を図りながら、今後も変わらず「ボトムアップ」を主体として、全身全霊で見附のまちづくりを進めていきます。
以上、令和6年度の市政運営に臨むにあたり、私の所信と基本方針を申し上げました。市民の皆様と議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。ご清聴、ありがとうございました。