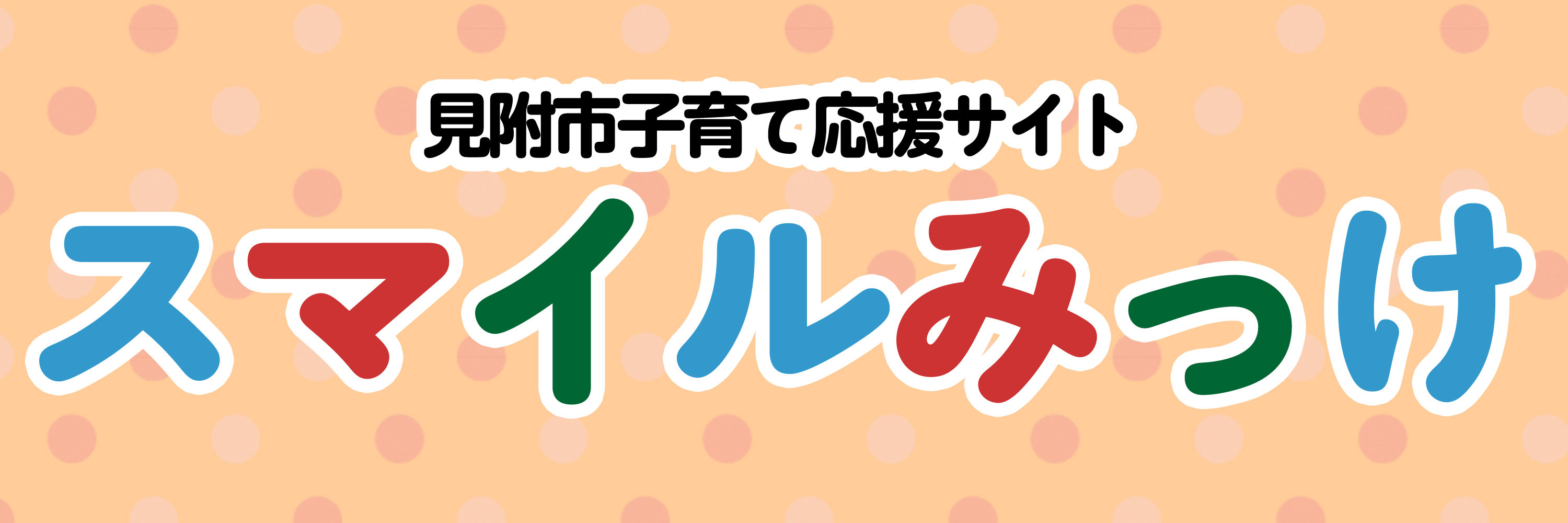本文
これまでお寄せいただいたご意見の紹介 令和6年度
パブリック・コメントの実施時に掲載した資料を、回答の発表後も一定期間、閲覧できるようにしてほしいです。また、回答時は質問内容を全文で掲載してほしいです。
今後、パブリック・コメントを募集し回答を市ホームページに掲載する際には、募集時の資料と質問文の全文を掲載するようにいたします。
市内のバスが通っていない区域にコミュニティバスを通すことを提案します。移動しやすく、得をするだけでなく、暑さや事故も防げると思います。(市内小学生からの提案)
見附市は市街地を中心にコミュニティバス、市外や市の中心をつなぐ路線バスが走っていますが、多くの人を乗せられるバスはある程度利用者が見込まれるところを走行する必要があります。バスが運行していない地域とコミュニティバスが走っている地域をつなぐためのデマンド型乗合タクシーやコミュニティワゴンを走らせることでお互いに足りない部分を補い合い、市全域で何らかの公共交通を利用できる仕組みとしています。
高齢者の方々が車の事故によってお亡くなりになる事例が多いことも承知していますので、見附市では免許を返納してもらった方に、バスやタクシーにお得に乗れるようになるサービスの実施や、先に説明した公共交通を整備することで、少しでも免許を返納しやすい環境を作るように努めています。
コミュニティバスを市内の全地域に走らせることは簡単ではないですが、デマンドタクシーやコミュニティワゴンをより利用してもらいやすいように改善していくなど、市内どこに住んでいても車を持っていない人たちが快適に移動できるよう取り組んでいきます。
信号機の青信号を長くすることを提案します。赤信号が長いと、夏は熱中症の危険も高くなり、冬は体調を崩してしまうと考えます。また、青信号が短いと、急いで渡らないといけないため、交通事故の危険性があります。(市内小学生からの提案)
信号機の青信号・赤信号の時間の長さは、車の通行量など色々なことを考えて警察の方々が決めています。
青信号が長くなると良いこともあると思いますが、信号の時間は、交差する2つの道路の交通量や、隣の交差点の信号機の青信号・赤信号の時間を比べながら、長すぎず、短すぎない時間を決めなければいけません。
警察の方々は、交通量の他に、時刻や右や左に曲がる車のことなどを考えて、青信号・赤信号の長さを決められていると思います。市としても、実際に現地を確認し、必要があれば警察の方にお話していきたいと思います。また、警察の方と直接お話しすることも可能ですので、ご提案してみてください。
自転車ヘルメットの貸出場を作ることを提案します。市内ではヘルメットを被っている人が少なく、全国では事故を起こして亡くなっているひとが何人もいるそうです。被っていない理由は「持っていない」「持ち運びが面倒」「高価で買えない」という内容が多いので、ヘルメットの貸出しを実現してほしいです。(市内小学生からの提案)
ヘルメットを着用して自転車に乗ることは、事故にあったとしても頭に重傷を負う確率が低くなるので、とても重要な取組みと考えています。
貸出しには、色々な人が利用したヘルメットの衛生面の問題があったり、貸出場の設置や常駐する人など多くの費用がかかったりと、課題があると思います。ヘルメットの貸出場も一つのアイデアですが、交通事故などによる危険性を減らすためには、自分に合ったヘルメットを自分自身で購入して手元に置いておき、必要なときにすぐ着用できるように用意しておくことが一番重要だと思います。
市では、市民の皆さんにヘルメットの必要性だけでなく、自転車利用のルールを知ってもらい、自転車による交通事故などを減らしていく取組みに力を入れていきたいと考えています。
市内に駄菓子屋さんを作ることを提案します。小学生も小さな子どもも、気軽に安いお菓子が買えて過ごしやすくなると思います。また、懐かしいお菓子を買うことができれば、高齢の方にも親しんでもらえると思います。(市内小学生からの提案)
見附市には、商店街に新たに店を出すときにお金を支援する制度があります。こういった制度を使って駄菓子屋さんにお店を出していただけるのが一番いいと思います。もちろん、駄菓子屋さんが生活するためにお金をかせげないといけないので必ずしもお店を出してくれるかわかりませんが、こういった人たちと会う機会があれば話をしてみたいと思います。
また、市内の各地域には地域コミュニティという団体がいて、地域のみんなが困っていることを解決したり、みんなが交流するイベントを行ったりしています。毎日は難しくても、お友達と一緒に駄菓子を食べて楽しめる機会を作ることができないか、地域コミュニティの人と一緒に考えてみるのはどうでしょうか。どんなことをすればみんなが楽しめるか、そして、見附市をもっと暮らしやすいまちにできるか、アイディアを教えてくれたら嬉しいです。
市の借金を返すことを提案します。使いたい金額だけを借りて、借りたらすぐ金利をつけて返すのはどうでしょうか。借金を返すことで、またいつでもお金を借りる事ができ、「早く返さないと」という気持ちにならなくてもよくなります。(市内小学生からの提案)
市による国や金融機関などから調達する借金のことを「市債」といいます。現在、見附市の市債は約200億円あります。
なぜ市が市債によって資金を調達する必要があるのかというと、ある年度に市にとって必要な大きな事業をする場合に、その年度に使えるお金がなくても市民の通常の生活に支障がないように事業を行うことが大切であるからです。例えば最近、見附市では新しく浄水場や、給食センターを整備しました。借金をせずにその年度の市の歳入(収入)のみで整備費用をまかなったとしたら、その年度は市民サービスにあてる費用が足りず、サービスを削る必要が生じたと思います。例えば、学校の修理や備品の購入、放課後児童クラブの運営、道路や公園の修理や管理などのサービスの費用が挙げられます。無理して借金を一気に返せば、借金をしない場合と同じで、返済した年度の市民サービスにお金が回らなくなります。
また、先ほどの浄水場や学校給食センターなどの施設は、その年度に水を飲む市民の皆さんや給食を食べる子供たちだけではなく、整備後30年とか50年にわたってその施設の恩恵を受けることになります。
このことから、将来に過度の負担にならない形で市債を借り、市民サービスに影響を及ぼさないよう計画的に返済を進めることが重要と考えています。
市債などの財政運営も含めて見附市の将来のことをしっかりと考えながら、みんなが暮らし満足No.1と思えるまちづくりを進めていきます。
生活習慣病の予防のために、給食を販売することを提案します。栄養士さんが考えた給食を販売することで、多くの人が栄養バランスのとれた食事をすることができると思います。(市内小学生からの提案)
学校給食センターでつくった給食を「お弁当」として、お店で販売するためには、飲食に関する営業許可・販売許可を取得する必要があります。市のような公共の自治体は営利目的を有していないため、市民の皆さんへの給食の提供は残念ながらできないことになります。また、市の施設である給食センターを有効利用している事業者さんが給食と同じお弁当をつくって販売することは可能です。ただし、お弁当の容器代や販売する人の給料、お弁当を運ぶ運搬費などを含めて、お金がかせげるかどうかを事業者さん自身で判断いただくことになるので、提案を伝えてみたいと思います。
学校給食センターでは、「給食だより」や「学校給食レシピ集」を市のホームページで紹介していますので、ぜひ調理にチャレンジしてみてください。
また、見附食育応援サイトでは健康増進や生活習慣病予防に役立つ「食育れしぴ」や「食育献立」を紹介して生活習慣病の予防に役立ててもらっていますので、こちらも参考にしてみなさんに紹介していただけたらと思います。
これからも健康づくりのために、ご協力をよろしくお願いします。
市内の公園の遊具を増やすことを提案します。小学生、中学生の体力が年々低下していて、これでは子どもや大人が健康ではなくなるかもしれません。遊具がたくさんあり、楽しく健康に良い遊びができる公園であったら、子どもたちも親も嬉しいと思います。(市内小学生からの提案)
いただいた提案から、皆さんに健康にすごしてもらうために、公園をより良くしてほしいという気持ちが伝わってきました。私も多くの子どもたちに外で思いっきり遊んでもらえるような公園にしていきたいと思っています。
ただし、公園の遊具を新しく作ったり、皆さんに安全に使っていただけるよう点検や修理を行ったりするには多くのお金がかかります。今後ともアンケートをとるなど、子どもたちを含めた市民の皆さんの声を聞きながら、遊具を含めた公園のありかたを考えていきたいと思います。
市内に遊び場(アスレチック)を作ることを提案します。小学生は遠くへは行けないので、近くのプレイラボなどで遊ぶことが多いです。(市内小学生からの提案)
プレイラボみつけは、「市内に雨の日や雪の日でも体を動かすことができる屋内の子どもの遊び場や学びの場としての施設が欲しい」という、市民からの要望を受け、令和2年から約2年かけて、市民委員の方々やキッズサポーターの皆さんとワークショップを開き、どんな施設にするかについて、たくさんの意見を出し合いながら、みんなで相談して作ったものです。
提案いただいたアスレチックを含む遊び場の検討についても、今後ともアンケートをとるなど、子どもたちを含めた市民の皆さんの声を聞きながら考えていきたいと思います。
今後も子どもたちからのたくさんの意見を聞きながら、子どもたちみんなが元気で、親も安心して子育てができるような、笑顔かがやくまちにしていきたいと考えています。
総合体育館の使用料金を少し上げて空調設備を導入できませんか。気温の上昇のため夏場は運動が出来る状況になく、健康を害することが考えられます。
ご指摘のとおり、近年の夏の猛暑は、利用者の健康面への影響が心配されます。そのため、総合体育館では入口に熱中症指数モニター(温度計)を配置するとともに、こまめな水分補給をお願いするなど来館者に注意を促しながら、ご利用いただいています。
総合体育館は、大きな施設であるため大型の空調が必要になります。また、併せて断熱改修工事も必要になることから、空調設備の設置については、多額の費用が見込まれます。そのため、総合体育館にすぐにエアコンを設置することは難しい状況です。
一方で、市内の公共施設のあり方について今後検討していくことを考えています。特に、総合体育館は築53年の施設で老朽化が進んでいることから、抜本的に今後のあり方を考える時期が来ています。いただいたご提案も踏まえながら、スポーツ施設の在り方等を総合的に検討していきたいと考えています。
町内の配布物の回数を月2回から1回に変えるなど、回数の調整を検討できませんか。
市としても、町内役員の皆様の作業負担は課題の1つと考えており、電子媒体の活用や配布資料の種類について検討を行っています。ご提案いただいた月1回の配布回数なども含め、どのような形が負担の軽減につながるのか、今後も検討していきます。
ネーブルみつけのエレベーターが使えず、2階から歩行器で降りられないことがありました。エレベーターが動くようにしてほしいです。
ネーブルみつけ2階の屋上駐車場からの入口には、職員呼び出し用のインターホンを設置しています。このインターホンのボタンを押しますと、職員が駆けつけ、階段を降りるお手伝いをいたしますので、お困りの際は遠慮なくお申し付けください。この度のご意見を受け、より分かりやすくなるよう表示の改善を検討していきます。
なお、ご指摘のとおり、ネーブルみつけのエレベーターは現在使用できない状態となっています。すでに設備が老朽化していることから、設備全体の入替えなどに多額の費用がかかるため、現時点で改修の予定はありません。何とぞご理解とご協力をお願いします。
税の納付について、二次元コード付き納付書の対象を拡大して利便性を高めてほしいです。現在、見附市では固定資産税・都市計画税、軽自動車税のみが対象ですが、他県では市民税・県民税・国民健康保険税なども対象になっています。
当市としましても、より多くの税目を二次元コードの読み取りから納付可能とすることは、納税する方の利便性を高めるものと考えています。
対象の税目の追加については、令和7年度に行うシステム改修に合わせて、令和7年11月発行分から市県民税(普通徴収)・国民健康保険税の納付書を二次元コード対応にする予定です。それまでの間はご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。
パブリック・コメントについて市から回答後に、再質問・再要望の機会を、短期間、設定することはできませんか。
再質問を受け付けることは、条例案等の作成を今よりも前倒しして行う必要が生じます。このことは、議会への提出や策定時期から逆算し、時間的にも厳しい状況で作成業務を進めている現状を考慮すると難しいのが実情です。一方で、いただいた質問とその回答がかみ合わなかったり、回答が含まれなかったりすることは、あってはならないと思いますので、的確かつ丁寧な回答作成を行うよう改めて徹底させていきます。
なお、パブリックコメントの手続きの流れの中で、再質問の受け付けは難しい状況ではありますが、日頃から市民の皆さんの問合せには対応していますので、必要に応じて担当課へお問合せをお願いします。