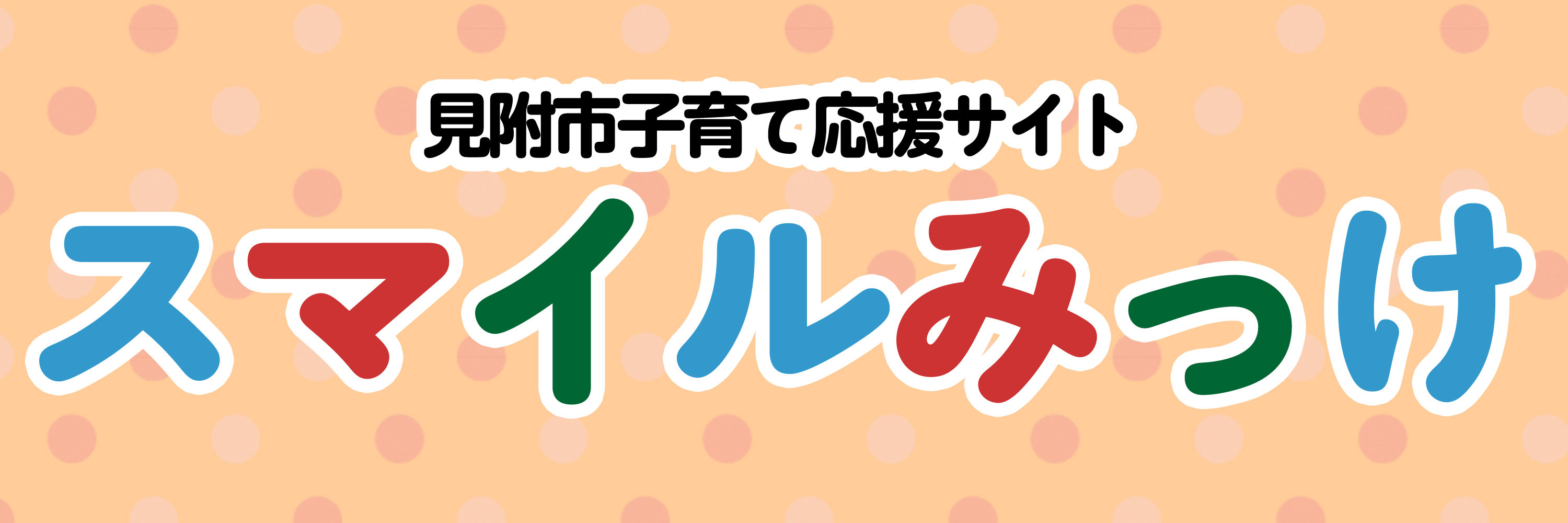本文
写真で見る 東日本大震災に関する見附市の様子
4月14日 2頭の子ヤギが避難所を訪問
全国山羊ネットワークの今井明夫代表(三条市)が、生後3週間のメスの子ヤギと1か月のオスの子ヤギを連れて、中央公民館と今町体育館を訪れました。

↑子どもたちは、子ヤギに白菜やミルクをあげながら、「かわいいねー」「ミルク飲むの早いねー」と楽しんでいました。

↑今井さんは「ヤギと触れ合うことで、子どもも大人も笑顔になってほしいと思って」と話していました。
4月12日 海の家にロシアモスクワの児童から絵などが届きました
ロシアモスクワ州の学校に通う児童が被災した日本の子どもたちのためにと書いた絵やメッセージなどが、海の家に届けられました。

↑モスクワの児童から届いた絵、メッセージ、ぬいぐるみ。
4月11日 震災から1か月 2時46分に市内各避難所・公共施設で黙祷


4月8日 市立病院に「災害支援外来」(内科)を開設
東京医科歯科大学医学部附属病院の協力で、4月~5月の第2・第4金曜日に、市立病院に災害支援外来(内科)を設置。

↑災害支援外来の診察室。避難者を優先に診察します。

↑中央公民館、今町地区体育館の避難所の代表者が担当医師と面会。斉藤一志さん(南相馬市)は「避難してきた方々はだんだんと疲れがたまってきています。何かあったときにはよろしくお願いします」と話していました。
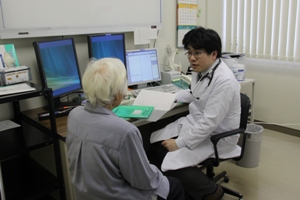
↑災害支援外来を受診する避難者
4月5日 避難所に誕生した新しい命を祝福
3月17日に海の家に避難して来た、菅野美樹さんに3月30日、長女きらりちゃんが誕生。名前は「きらきらとかがやく子に育ってほしい」と長男の海翔くんが命名。

↑美樹さんと次男の優翔くん、長女のきらりちゃん。美樹さんは「地震のときは周りのものを抑えるので精一杯でした。無事に生まれてきてくれて本当にうれしいです。かわいくてしょうがないですね」と話していました。

↑新しい命の誕生を祝福して、4月5日、久住市長(当時)が子どもの肌着などのセットをプレゼントしました。
4月3日 みらい市場が市民と避難者との交流イベントを開催
ネーブルみつけで見附の特産品などを扱う「みらい市場」は、見附に避難してきている人たちを元気づけるイベントを行いました。午前、午後の2回行われたうち午前の回では、会場に100人近くの人が集まり、アトラクションを楽しんだり、つきたての餅を食べたりして、楽しんでいました。
みらい市場の代表、堀川岩男さんは、「見附の人はショウシガリ屋(恥ずかしがり屋)です。このイベントで避難してきた人と市民が気軽に話すきっかけになればいいと思って企画しました」と話していました。


アトラクションとして、よさこいソーラン、マジック、オカリナ演奏が行われました。中央公民館に避難している女性は、「楽しくて元気が出ました。来てよかったです」と話していました。
つきたての餅があんこ餅やきな粉餅、雑煮にされて振る舞われました。もちつきをした4歳の男の子は、「楽しかった。杵が重かった。あんこもちがおいしかった」と話していました。
3月31日 避難者の子どもたちを対象に学習支援教室を行いました
市教育委員会は、避難して来た子どもたちの学習を支援する教室を開きました。これは、民間学習塾「くもん今町教室」を経営する坂口孝子さん(今町5)からの提案で実現したものです。坂口さんは「私も7・13水害のときに中之島教室が全壊してしまい、自衛隊やボランティアの方に助けてもらいました。見附に避難している子たちにも、避難している間は支援をしてあげたい」と話していました。4月から中学2年になる佐藤愛理奈さん(南相馬市)は、「勉強道具が何もなかったので、しばらく勉強できなかった。学校に行く前にちょっとだけでも勉強できてよかった」と話していました。 
↑子どもたちは、学年に合わせて算数や国語の問題を解きました。筆入れや鉛筆はすべてこの塾に通う子どもたちの父兄が寄付したもの。

↑学習終了後、今町小PTAや今町5丁目などの地域人の協力で、豚汁、炊き込みご飯などの昼食が振る舞われました。
3月30日 市内の避難所で新潟大学落語研究部が寄席を披露
「字が読めない男の話」など、新潟大学落語研究部の3人がそれぞれ落語を披露。避難所に笑顔と笑い声が沸きました。新潟大学落語研究部部長の中島三四郎(ゑちご亭充家)さんは、「後輩の一人が大船渡市(岩手県)出身で、家族と一週間近く連絡が取れないと聞き、他人事ではないと感じました。自分たちが何か力になれればと思い、この活動を始めました」と活動への思いを語りました。 
↑落語を楽しんだ避難者の男性は「元気をもらいました。皆さんに負けないようにがんばっていきたいと思います」と力強く話していました。
3月28・29日 「ようこそ学校へ」市内の学校で避難してきた子どもたちと地元児童が交流
見附小・中学校、今町小・中学校で、避難して来た子どもたちと保護者を対象に、学校案内や児童と交流会などを行いました。3月28日(火曜日)、見附小学校では、パソコン学習、児童による学校案内、体ほぐし運動を行いました。お母さんの高野奈々さん(南相馬市)は、「子どもたちが元気に遊んでいるから、私たちもリフレッシュできました。今年1年生になる子がいるんですが、ランドセルも実家の押入れに入れたままで来てしまいました。子どもが学校に行きたいと言ってくれたから、子どもの気持ちを尊重したいと思っています」と話しました。娘の杏花さんは「初めての学校でドキドキしたけど楽しかった」と話していました。

↑見附小新6年生による学校案内。見学した人は「花がいっぱいできれいだね」と話していました。


↑避難者の女の子に優しくパソコンを教えていました。

↑子どもたちは体育館で、体育館で思いっきり走ったり、背中合わせや人間知恵の輪をしたりして、楽しんでいました。
3月23・24日 避難者の小学6年生4名の卒業を各避難所でお祝い
市内に避難してきた4名の小学6年生に、久住市長(当時)から「卒業お祝いメッセージ」、見附小学校からの寄せ書き、出身校の先生からのお祝いのメッセージなどが贈られました。会の中では、卒業生のご家族が、目に涙を浮かべる姿もありました。卒業生の一人の木元美里さん(南相馬市)は、「ほんとにありがたいと思っています。まさかここでできると思わなかった。でもやっぱり、みんなで一緒に祝いたかったという気持ちもあります」と話しました。

↑久住市長(当時)からお祝いのメッセージを受け取る卒業生(海・海ハウス)

↑久住市長(当時)からお祝いのメッセージを受け取る卒業生(今町体育館)

↑卒業を祝う会にあわせて中央公民館では、「被災した人たちのために、自分たちにできることはないか」と考えた見附中学校の2年生114名が、卒業生と避難者の方たちに向けて「変わらないもの」など2曲を合唱しました。
3月20・21日 見附青年会議所がネーブルみつけで支援物資を募集


↑紙おむつや水、食糧など2tトラック9台分の物資が集まり、被災地に運ばれました。
3月19日 見附ニット工業協同組合が避難者に450枚のニットを提供


↑避難者の方はニットを選びながら「あったかそうね~」とほほえんでいました。
3月18日 今町体育館に151名を受け入れました

3月18日 市役所1階、ネーブルみつけ、各公民館、今町出張所に募金箱を設置

3月17日 海の家「海・海ハウス」に避難者を受け入れ

↑海・海ハウスに107名が到着しました。

↑久しぶりの落ち着いた食事に顔を緩める姿も見られました。渡辺愛子さん(大熊町)は「自分の家がどうなっているかも見ずに、とにかく逃げてきました。向こう(福島)では寝られなかった」と語りました。