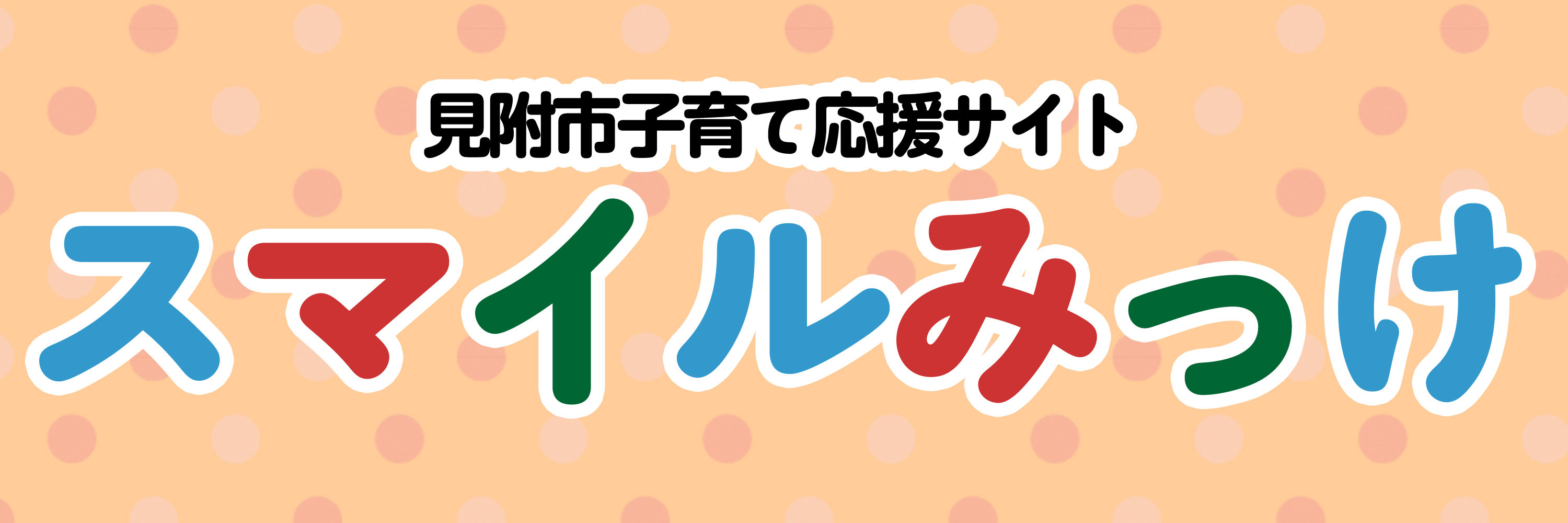本文
令和7年度 施政方針
本日ここに、令和7年3月市議会定例会が開催されるにあたり、市政運営に臨む私の姿勢と所信の一端を申し上げますとともに、令和7年度当初予算案の重点施策など、その概要をご説明申し上げます。
見附市では「暮らし満足No.1のまち」を目標に掲げ、7つの柱を軸とした市政運営を進めています。昨年9月に実施した「まちづくり市民アンケート」では、「住み良いまち」との評価が91.8%と過去最高を記録し、「魅力あるまちになった」との回答も73.6%と高い数値を示しました。今後も市民の皆さんに満足していただくためには、将来に向かって持続可能なまちとしていく必要があり、それには可能な限りの人口確保に取り組んでいく必要があると考えています。
その鍵となるのは、次世代を担う若者や子育て世代です。彼らが「住み続けたい」「戻ってきたい」「新たに住みたい」と思え、稼げる、暮らせる、子育てできる環境を磨くこと。そして見附の住みよさの戦略的発信こそが大切だと考えています。子育て環境については、昨年、保育園の新規参入やリニューアル、放課後児童クラブの拡充、駅交流施設「ミツケル」のオープンなどが行われました。教育面では、起業家精神を育む「みつけJobチャレ教育」の本格始動や、小中学校の最適配置に関する議論が最終段階を迎えています。また、「こども・子育てどまんなか条例」を施行したことも踏まえ、行政・地域・企業が一体となった子育て支援をさらに推進してまいります。加えて、企業誘致や農業振興を含めた若者に魅力ある産業・雇用の創出など、移住・関係人口の増加を図る施策を展開し、「若者に選ばれるまちづくり」を進めます。
もちろん、暮らし満足No.1のまちに向けては、若者世代だけでなく、あらゆる世代や境遇の市民が安心して暮らせる環境の整備も重要です。スマートウエルネスによる健幸づくりを継続しつつ、市立病院を核とした地域医療の充実、公共交通の利便性向上、そしてリスクの高まる大規模地震など災害への備えの強化に取り組んでまいります。さらに障がいのある方や認知症の方、不登校の児童・生徒など、多様な市民が共に支え合う「誰ひとり取り残さないまち」の実現を目指します。
一方で、新たに中長期財政見通しを公表しましたが、市の財政について、今は危機的な状況ではなく悲観しすぎる必要はないものの将来を見据えると楽観視できる状況にないことに変わりはありません。今年度は、歳入面ではふるさと納税の寄附額が当初の見込みを大きく超えて過去最高額となったほか、歳出面では予算編成時に各課毎に削減目標を設定して事業見直しを進めました。今後は本格的に着手する公共施設のありかたを見直していくなどの新しいニーズへの対応と並行して市民の皆様へ理解を求めながら着実に進めます。
以上のような方針のもと、職員一丸となって議論を重ね、令和7年度予算案をまとめました。
その新年度一般会計予算は、ふるさと納税の拡大や障害者介護給付事業の増加などが影響して199億8,000万円となりました。これは前年度に比べて10億7,000万円、5.7%の増となりました。予算規模は拡大しましたが、財政調整基金及び減債基金の取崩し額は前年度に比べて1億600万円の減額となっています。また、4特別会計の合計は85億7,300万円となり、前年度比3億6,800万円、4.5%の増、3公営企業会計の合計は85億3,550万円となり、前年度比8,450万円、1.0%の増となりました。それでは、新年度の取り組みにつきまして、「暮らし満足No.1のまち」実現に向けて重要となる7つの考え方をもとにご説明申し上げます。
1つ目は、『まちと産業を元気にする』です。
見附への移住・定住の促進としては、今年度策定している移住戦略に基づき、見附の魅力を効果的に発信するプロモーションを展開します。具体的には、首都圏在住者に向けたweb広告から、市の新しい移住PRサイトに誘導し、見附の魅力をPRします。そこから、移住検討者のニーズに合わせて市内の施設見学や先輩移住者の紹介などを組み合わせて行うオーダーメイドツアーや、お試し移住拠点の利用につなげ、見附市への移住者増加を図ります。さらに市民からの声掛けで移住した場合に支給する支援金制度を新設し、市民と力を合わせてPRに取り組んでいきます。また、市内での居住や就職を後押しするため、奨学金返済支援制度を令和7年度内に創設し、令和8年度予算案計上に向け検討します。さらに、国が提唱する2地域居住については、見附の住みよさと首都圏との距離やアクセスの点からも、見附市への移住定住策の1つとしての可能性を秘めており、プロモーションの工夫など取り組むべき方策について検討を進めます。
結婚促進策としては、市内で新婚世帯が生活を始めるための経費の支援や、県のマッチングサービスへの入会登録料補助を継続するほか、結婚に悩む市民を対象に個別相談会や専門家による一人ひとり合った伴走型支援を新たに実施します。
関係人口の拡大としては、今年度東京で初めて開催した「MITSUKE Meet up」は、見附出身者や見附に思いのある若者が集まったことから、つながりを継続することで見附市との関係を徐々に深め、将来の関係人口につなげていきます。また、今年度寄付額が大きく増加したふるさと納税者に対して、見附のさまざまな魅力を発信するとともに「見附さぽーた」への加入も促し、新規会員や関係人口の増加につなげます。
さらに学級数の減少が進む県立見附高校については、県内でのアクセスも優れ、魅力化が進めば市内のみならず、市外から多くの生徒を受け入れるポテンシャルがあると考えます。関係人口拡大の観点からも、同校の魅力化・特色化について積極的に県に要望しつつ、並行して市としても企業や地域とともにサポートできないか、高校関係者との議論を進めていきます。
交流人口の拡大として、「スポーツツーリズム」については、地域経済の活性化と市民との交流促進の両面から、合宿等受け入れ団体へのフォローを継続して進めます。特に大会開催が定着した女子野球をさらに発展できないか、スポーツ協会とも連携しながら模索していきます。「長野・新潟ガーデンロード」については、構成施設等と連携した取り組み強化の結果、今年6月には旅行会社によるガーデンロード施設を巡るツアーも実現することになりました。今年度外国語パンフを宿泊施設や企業に配布した「インバウンド」や国の八十里越道路整備など様々な人の流れや動向をとらえながら、観光物産協会や市内事業者とも連携して、発信強化や市内他施設への誘導など経済効果を高める取り組みを進めます。
地場経済の活性化に向けては、企業の人材不足解消とライフスタイルにあわせた多様な働き方を望む市民ニーズに応えるため、デジタル技術を活用した求人求職マッチングシステムを新たに構築します。また、国の物価高騰対策交付金を活用して、子育て世帯にみつけ子育て応援券を配布し、事業市内店舗での消費を喚起します。ニット産業については、展示会出展等の各社の販路開拓について、支援を拡充するとともに、五泉との連携の必要性を議論するなど業界に寄り添っていきます。夜のタクシー不足対策については、今年度のナイトコミタク実証運行も踏まえ、市内飲食店の声を聞きながら、費用や体制などの面から実施可能な仕組みを検証し、長期的な視野も含めて今後の対応を検討していきます
農業振興については、課題となっている次世代の地域農業を支える担い手の確保や育成を図るため、農業者による既存の組織内に「若手の会」「女性の会」などの部会を立ち上げ、市の担当も参加し、農業者同士の連携強化を図りながら将来の農業のために打つべき一手をともに考えていきます。また、将来を担う若手農業者の参入や継承・育成を支えるため、既存の水稲用機械等導入補助に若手農業者を優先して採択する「若手農業者経営開始支援」メニューを新設します。ニラについては、関係機関と連携しながら、品質向上と出荷量安定化を目指します。鳥獣被害対策については、近年イノシシなどによる農作物への被害が急増していることから、罠を新たに購入し取り組み対策箇所を拡大するほか、イノシシ、クマ等の捕獲に対して報償金を支払う制度を創設します。
新たな事業の創出については、企業誘致環境整備に向けて、地域未来投資促進法の基本計画や企業設置奨励条例の見直しに向けて検討を進めるとともに、経済産業省の伴走支援専門家のアドバイスを受けながら、新たに企業立地が可能となる環境の整備に取り組みます。また起業創業支援については、初期費用補助や、定住自立圏自治体と連携したセミナーや相談会などを継続します。さらに今年度開催した職員による未来検討ワーキンググループでは、見附市在住の若者が夢を実現でき活躍できるまちであるための「若者チャレンジ応援事業」の提案があり、令和8年度の制度化に向けて検討を進めます。
住宅都市環境の整備では、ウエルネスタウンについては、その価値を可能な限り保ちながら販売を加速するため、個別住宅においては、補助額の見直しやハウスメーカーと連携した新たな販売促進策を展開するとともに、集合住宅においては、民間を事業主体とする手法を最優先として、活用に向けた取り組みを進めます。空き家対策については、新たに協定を締結した弁護士会とも連携した特定空き家等の対策強化や、所有者への適正管理の働きかけを行うとともに、来年度予定の空き家計画改正において、空き家の利活用に向けたさらなる一手について所有者ニーズを把握しながら検討します。
公共交通については、コミバスは老朽化した車両の更新を行いながら現在の利便性を維持します。コミバス等が走行していない地域については、コミュニティワゴンの活用策を各地域コミュニティの意向も踏まえながら自家用有償など制度の見直し動向を見据えつつ、デマンドタクシーのありかたと併せて検討していきます。運営会社のサービス終了にともない休止しているレンタサイクルについては、既存車両を有効活用しながら新たな形での再開に向け準備を進めます。
2つ目は、『子育て・教育』についてです。
働きながら育てられる環境の整備については、市内企業による子育てしやすい職場づくりをより一層後押しするため、子育てしやすい職場環境の整備を行った企業に対し引き続き奨励金を交付するほか、事業者が従業員に育児休業を取得させた際の補助金の交付要件を見直し、市内在住者のみだった対象者を市外に居住して通勤する従業員にも拡大します。また、若者の採用・育成に積極的な中小企業「ユースエール企業」として国の認定を受けた企業に対して、見附市設備投資応援補助金の補助率及び上限額を拡充します。
市内企業を先導するため市役所においても進め、多子世帯の子の看護休暇取得日数の充実や、育児休業取得職員等の補充のために秋採用と異動の定例化、テレワーク活用の試行など、他の理由と併せて多様な働き方を可能とする職場環境整備に取り組みます。
子育て・出産の負担軽減については、物価高騰対策として妊娠中から18歳までの子育て世帯を経済的に支援するため、市内店舗で活用できる「みつけ子育て応援券」を配布します。保育料については、全体的に1割程度下げるとともに、従来の第3子完全無料に加えて第2子1・2歳児保育料を半額公費負担にして多子世帯の経済的負担を軽減します。また、出産後の母子の心身ケアや育児相談を充実させるため、これまで訪問、通所、日帰り型の産後ケアに加えて、新たに宿泊型産後ケアも実施します。さらに子育て支援センターでは、体調不良時や出かけるのが苦手な親子などを支援するため、オンラインでも相談が受けられる体制を整備します。
続いて子どもの居場所・遊び場・活動の充実についてです。
中学生のスポーツ活動・文化活動の選択肢の確保については、子どもたちのニーズや生活スタイルを把握しながら、「部活動地域移行」のみならず「活動体験の機会提供」と一体的に取り組みます。来年度は、スポーツ系種目を拡大するとともに文化系の美術活動を開始するほか、既存の部活動種目にない活動機会を提供する「わくわく体験型事業」を試行します。放課後児童クラブについては、少なくとも帰宅後の生活が心配な小学3年生までは希望する全児童の受け入れを可能とする体制を確保してまいります。また、子どもたちの移動手段の充実の一環として、地域コミュニティが行うコミュニティワゴンを活用したプレイラボ送迎実施に向けた調整等の支援を行います。さらに増加したふるさと納税寄付金の一部を子どもたちのために見える形で活用するため、こどもや保護者からのアンケート調査結果を踏まえ、公園等における大型遊具整備に向けた検討に着手します。
取り残されることなく子どもたちが育つ環境づくりとしては、不登校の児童生徒への対応を強化するため、子どもの状態や家庭環境に応じて、本人・保護者に支援・助言し、必要な関係機関につなぐための専門家であるスクール・ソーシャル・ワーカーを新たに配置し、早期の相談体制、関係機関への連携など重層的な支援を実施します。児童発達支援相談については、新たに「小児科医師による相談会」を行い相談支援の強化を行うことで、就学前までの子どもの発達に関する相談、支援体制の充実を図ります。
見附らしい教育活動の充実に向けては、「みつけJobチャレ教育」については、子どもたちに見附で活躍する事業所等を知ってもらい、地域のよさを再発見してもらうため「みつけJobチャレ図鑑」を作成するとともに、起業体験や出前授業、アイデアコンテストなどの取り組みを推進します。また、中学生を対象に、将来に希望を見出し、進学・職業・結婚・育児・生きがい・ワークライフバランスなどのライフイベントに柔軟に対応できるための必要な知識の習得と自分の理想とするライフデザインを具体的に考える機会を提供する「ライフデザインセミナー」を新たに開催します。
子どもたちが安心できる環境整備については、学校施設長寿命化計画に基づき、引き続き名木野小学校の長寿命化改良工事を行うほか、新潟小学校の空調設備を改修します。公立保育園の園児安全対策に向けては、不審者対策としてカメラ付き電子施錠の設置を行うとともに、保育室のエアコンの入替を実施します。安全な通学路の整備については、葛巻反田線において車両の速度抑制対策として新たにハンプや狭さくなどの設置の可能性について実証実験を通じて確認するほか、県道見附下新町線の整備を促進するなど安心して子どもたちが通学できる道路整備を進めます。
将来に向けた子育て・教育のあり方については、昨年4月に施行した「見附市こども・子育てどまんなか条例」や今年度中に策定予定の「見附市こども計画」について、市民・地域・企業などへの周知・啓発をより一層進め、「こどもどまんなか」の理念の浸透や理解醸成を図ります。将来の学校教育環境については、今年度中に予定されている見附市立学校配置等検討委員会の答申を踏まえつつ、アンケート等により特に子育て世代を中心に市民ニーズを把握しながら、令和7年秋を目途に「小中学校適正配置計画案」の策定・公表を目指すなど、子どもたちの将来を第一に考えた環境改善を進めます。
3つ目は、『健幸』についてです。
障がい者施策の充実については、本定例会に案を提出した「見附市障がいを理由とする差別のないだれもが共に暮らせるまちづくり条例」について、市民や企業等に対して幅広く周知を進め、障がいのある人に対する理解の醸成を図ります。また、日常生活用具に非常時の電源確保を想定した蓄電池や、障がい児の療育を兼ねた意思疎通支援用具を追加するほか、障がいのある当事者の団体等の自発的な活動の促進と活性化を目的に、障がい者の活動機会を創出する事業や組織の立ち上げを支援する制度を創設します。さらに障がい者雇用の推進も引き続き進めていきます。
誰もが安心して暮らせる社会の構築に向けては、高齢、障害、子ども、生活困窮といった枠組みを超えた一体的な相談支援を行う重層的支援を本格的に展開し、庁内外の関係機関との連携を深めて支援体制の充実を図ります。また判断能力が十分でない認知症や知的障害、精神障害の方の権利を尊重、擁護する「成年後見制度中核機関」を設置します。増加している若者の自殺対策としては、従来から実施しているゲートキーパー養成講座について市内企業とより一層連携するほか、現状の課題にあったさらなる取り組みを検討していきます。LGBTQ+をはじめとした人権啓発については、まずは市職員が研修等を通じて対応力向上を目指すほか、令和8年度の人権教育・啓発推進計画改定に向けて課題の把握を進めます。
地域医療体制の充実については、引き続き現在または将来不足する診療科目を手厚くした新規診療所の開業資金を補助する支援制度を継続し、関係機関への働きかけを積極的に行っていきます。市立病院の医師確保に向けては、獨協医科大学の地域枠医学生への修学資金貸与を継続し、令和7年度に新たに1名を加え合計2名の医学生が卒業後5年間勤務します。
健康増進施策の進化に向けては、物価高騰対策と外出促進を目指して75歳以上の方と自動車運転免許を返納した方に対して市内公共交通がより気軽に利用できる「高齢者お出かけ応援券」を配布します。妊産婦を主な対象として運動と交流を促進する「マムアップパークby健幸スマイルスタジオ」は、開催場所の工夫や他のイベントとの連携を検討するなど、事業理解の促進と利用者の拡大を図ります。健幸フェスタについては、企業と連携してニーズをとらえた新たな試みができないか検討します。
環境問題への取り組みとしては、次期最終処分場の基本設計を完了させるとともに、令和8年度にかけて周辺の生活環境への影響調査を実施します。また、脱炭素や環境問題の啓発のため、クリーン作戦やエコアクション等のイベントにおいては、より多くの市民参加を進めるため、新たな企業への参加呼びかけを行い、市民団体とも連携させた啓発に取り組みます。
4つ目は、『安心安全』についてです。
地震等災害に備える体制の整備については、昨年末には市役所庁内の停電により非常時における業務継続の重要性を再認識させられたことも踏まえ、地震等大規模災害に備えた全庁的なBCP(事業継続計画)を改めて作成し、訓練等を通して検証します。また、指定避難所以外に避難者の様態や期間などに応じた避難先の幅を広げるため、民間賃貸住宅や宿泊施設活用に向けた協定締結を検討します。孤立が想定される集落については、指定避難所へ避難できないことも想定されるため、代替避難先や備蓄のありかたについて検討していきます。総合防災訓練については、一時避難を全市一斉で行いつつ、毎年重点地区を設定して指定避難所の立ち上げ・運営や共助による要支援者避難など多様な対応の確認を行います。
地震等に備えた施設やインフラの安全対策強化については、住宅における耐震化をより一層促進するため、住宅耐震改修費の補助上限額を引き上げます。また、大規模地震で落下する恐れのある大規模ホールの吊り天井については、中央公民館で取り外す耐震化工事を行うほか、文化ホールについても改修方法の検討を進めます。さらに埼玉県で発生した下水道管破損による道路陥没事故を踏まえ、周囲への影響が大きい内径1m以上の下水道管の緊急点検を行いましたが、今後とも計画的な管路点検や老朽管の更新、耐震化を進めます。
水害等対策施設の整備としては、貝喰川流域の浸水被害を軽減する県の大規模改修事業の早期完了に向け、県の委託事業である埋蔵文化財の発掘調査を継続して実施します。また浸水対策として芝野町のアンダーパス1か所に浸水検知センサーを設置し、豪雨時の速やかな対応につなげます。また、土砂災害特別警戒区域からの住宅移転を支援するため、住宅の移転等に係る費用の一部を補助します。
持続可能な雪害対策としては、持続可能な除雪体制の確立に向けて、体制維持が厳しい除雪業者への除雪機械のリース台数を拡大するほか、除雪待機料や機械維持費用に関して国の財政的支援を要望していきます。消雪パイプ施設の維持については、各消雪組合における持続可能な管理運営に向けて、相談を積極的に受けて課題解決に向けた対応を検討していきます。
消防力の維持充実については、老朽化した救助工作車や積載備品を更新し、救助業務の充実強化を図ります。増加する救急需要への対応は、救急車要請の是非を相談できる電話相談窓口やスマホアプリの周知、講習会・イベント活用など、消防、病院、保健師等が幅広く連携して効果的に啓発していきます。さらに消防団の充実に向けて、活動単位の統合を含めた組織再編や地域コミュニティなどとの連携の必要性について検討します。
原子力防災については、豪雪時等複合災害時での避難や除雪作業等のありかたや、相応の負担に対応した経済的支援等について国や県に要望を行っています。避難のありかたや方針については、現在県で1月の住民避難訓練を踏まえ検証を行っており、市ではすでに課題について意見・要望していますが、引き続き県の検証動向を注視してまいります。
5つ目は『市民の皆様に寄り添う』です。
市民の皆様との意見交換は、市政運営の土台としており、引き続き「ふれあい懇談会」を月1回ペースを目途で開催するとともに、職員共々さまざまな機会をとらえて市民の皆さんと交流し、課題や市民ニーズの把握に努めます。
情報発信の強化に向けては、市公式LINEは、緊急時の情報共有などで最も重要なツールとなることは能登半島地震の被災地で実証されており、現在約5,300人の登録者数のより一層の拡大に向け、様々な場面を活用して全庁的な対応で登録強化を図ります。また政策面の話題をあらゆる世代の市民に伝えられるよう、広報みつけの充実に加えてYoutube等のSNSでの発信を検討します。
ICTの活用については、新たにこれまで紙のカードで運用していた子育て応援カードを市公式LINEの機能に追加搭載することでデジタル化するほか、公共施設の予約システムについては、キャッシュレス決済に対応した新たなシステムに更新するなど、利用者の利便性の向上を図ります。また市役所庁内ネットワークの無線化を図り、ペーパレス化の推進や業務効率化につなげます。
市民サービスの向上としては、複雑化する女性相談に対応するため、有資格者の女性相談支援員を配置し相談の強化を図ります。加えて、消費者トラブルの未然防止を目的に、新たに悪質商法防止講演会を実施します。
6つ目は、『あらゆる力を結集する』です。
地域コミュニティについては、全地区で設立されて6年が経過し、人材確保などの課題はあるものの自立・成熟化が進み、地域課題の解決に向けた一層の役割が期待されます。事業の企画立案において防災や福祉、多世代交流、移動手段など多岐にわたる課題を意識していただけるよう、働きかけやサポートを充実させていきます。また地域コミュニティと生涯学習を推進する公民館の適切な役割分担のもと、来年度から公民館における職員配置体制や事業を見直し、地域コミュニティの成熟に向けたサポート強化にシフトします。
町内会運営については、町内会の課題把握や組織運営に関する相談に積極的に対応し、事務効率化や統合の必要性、地域コミュニティとの連携など組織の状況に応じた助言を行っていきます。また、役員等の負担軽減を図るため、市からの配布物の量や回数を削減するとともに段階的にデジタル化を検討します。
市民活動への支援については、市民活動支援センターの6月オープンに向けた準備を進めるとともに、特定の団体による社会課題解決に向けた活動や、各種市民活動団体の窓口機能の確保に向けた取り組みをサポートします。市民活動支援補助金についても補助率を見直すことで、活動をスタートしやすい環境を整えます。また、夏期・冬期における集会施設の室内環境の改善を支援するため、冷暖房設備整備を補助対象に加えます。
職員力の強化に関して、職員提案については、今年度事業につながらなかったものについても来年度補正や令和8年度の事業化につなげます。未来検討WGについて、職員研修の一環として今後も継続するほか、研修自体も業務改革や多様な視点の取入れに対応できるよう研修内容を充実させていきます。今年度から開始した加茂市、小千谷市との3市合同勉強会は、来年度は今年度とは異なるテーマで小千谷市にて実施する方向で調整しています。さらに来年度から登用予定の見附みらいづくり最高戦略監(CSO)については、全課統括する立場で公共施設の最適化をはじめとした取り組みを進めてもらうなかで、職員のさらなる力量形成にもつなげていきます。
7つ目は、『行財政検証』についてです。
大型事業については、駅周辺整備事業のうち、自由通路についてはJRとも調整しながら多方面から既存跨線橋の安全性を確認しているところであり、この結果を踏まえてできるだけ早い段階に方向性を示したいと考えています。
耳取遺跡事業は、アクセス道路の安全性確保等に課題が生じたことから再検討を進める一方、現況の地形や環境のままでの遺跡地内の積極活用に向け、地元市民団体の取り組みを支援するほか、地域住民と連携したイベントを実施します。
また、農業集落排水を公共下水道に統合し汚水処理施設の維持管理の効率化を図るほか、地域の民間活力を用いて効率的に施設の維持管理・更新を行う「ウォーターPPP」の導入可能性調査を、今年度に引き続き実施します。
既存事業の見直しについては、各課削減目標を立てて取り組んだ結果、具体例として、断熱改修リフォーム助成の見直しや、嘱託員配布回数減による効率化、小中学生音楽鑑賞会の休止、公民館事業の見直し、マリッジさぽーたや婚活イベント開催支援の休止、事業持続性確保のための健幸ポイント交換率見直し、運動メニュー提供システムや健幸アンバサダー関連講座の廃止、イングリッシュガーデンの植栽アドバイス業務の見直し、老人いこいの家の入浴事業廃止などを行い、必要に応じて代替事業を行いながら歳出削減を図りました。令和8年度予算編成に向けても、必要性の低下しているものを中心にさらなる削減に取り組みます。
歳入確保に向けては、ふるさと納税については、寄付額が1月末までの集計で昨年度の約9倍に増加しましたが、寄付額の増加に向け、返礼品の約95%を占める米の安定確保を図るとともに米以外の返礼品開発などに取り組みます。また、昨年度よりも実績を伸ばした企業版ふるさと納税、イングリッシュガーデン協力金についても、さらなる増額に向けた取り組みを進めます。他にも、本議会で提案した斎場や総合体育館使用料をはじめとした公共施設利用料などの見直しによる受益者負担の適正化や、着実な債権整理の実施、新しい制度による国県支出金や有利な地方債を活用し、さらなる歳入確保に努めていきます。
公共施設の見直しについては、財政体質の改善を図りながら将来を見据えた持続可能なまちづくりを進めていくため、利用状況や老朽度、市民や時代のニーズを分析し、廃止・集約や複合化、運営方法の見直し、民間活力の導入、新たな施設整備など、施設の再編や有効活用を検討していきます。
以上、「暮らし満足No.1のまち」実現に向けて重要となる7つの考え方を中心に、令和7年度、見附市が取り組もうと考える主な施策について、その概要を申し上げました。
令和7年度は、市の最上位計画となる「第5次見附市総合計画」の計画期間10年間の最終年度であることから、次期総合計画の策定に向けた本格的な議論が始まります。これまでの施策の検証・見直しをしっかりと進めながら、見附の現状を改めて分析し、市民の皆様の声や新たな課題、ニーズを踏まえた、市の中長期的な方向性を示していく必要があります。私自身、大切なキーワードは「未来」だと考えております。未来に向けて、先人の皆様が培ってきた見附の良さを継承しつつ、時代や実情に合った見直しを進め、5年10年先の未来を見据えた、持続可能で希望が持てる将来計画をお示ししてまいります。
これからも職員との議論やボトムアップの政策づくりを基本としつつ、丁寧な説明を心掛けながらも変化を恐れずさまざまなことにチャレンジしてまいります。そして市民の皆様、地域やボランティア団体、企業や業界団体など、あらゆる力を結集し、誰もが「暮らし満足No.1のまち」と思えるまちづくりを、皆様とともに推し進めてまいります。
以上、令和7年度の市政運営に臨むにあたり、私の所信と基本方針を申し上げました。市民の皆様と議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。ご清聴、ありがとうございました。