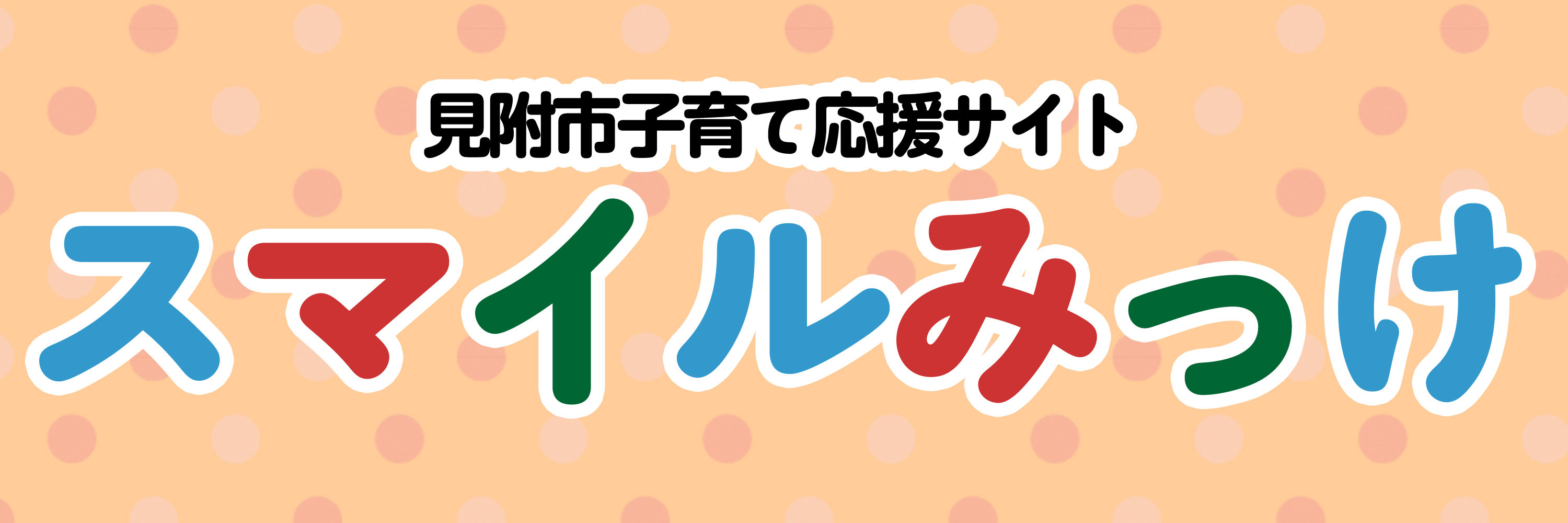本文
06 入澤達吉生家跡

入澤達吉は、1865(慶応元)年、入澤家の長男として生まれ、12歳まで今町で過ごしました。父・恭平が陸軍軍医として新潟に単身赴任のため、ほとんど父親不在での生活でした。達吉は母・唯子の勧めで蟠(ばん)龍(りゅう)塾(→「18」参照)・押野見塾に通ったほか、親戚が医師や神官だったため、そこに預けられ厳しく教育されました。
1873(明治6)年(9歳)、父が勤務中に脳溢血で亡くなると、12歳の時、東京の叔父・池田(いけだ)謙(けん)斎(さい)(日本最初の医学博士)の勧めもあり上京。母子ともに池田邸に寄宿し、私塾(漢学)に通いました。漢詩の素養はその時身に付けたものと思われます。
1877(明治10)年(13歳)、東京大学予科に入学。本科へと進みひたすら勉学にはげみ、卒業後はベルツ博士の無給助手として学内に勤務しました。
1890(明治23)年(26歳)、叔父の援助もありドイツに自費留学し、ストラブルヒ大学に入学。のちベルリン大学に移り、1894(明治27)年(30歳)に帰国。
すぐさま宮内省侍(じ)医局(いきょく)勤務、東宮殿下(のちの大正天皇)付を命ぜられました。1895(明治28)年、東京帝国大学助教授に、1901(明治34)年には同教授に就任。翌年、恩師ベルツ博士の退任の後を受け、大学内で入澤内科を開設しました。
1912(明治45)年に欧州視察を命ぜられ、欧州、米国の医学の実情を2年間にわたり視察し帰国。1920(大正9)年には、大正天皇侍医頭(じいかしら)の御用を命ぜられました。
1926(昭和元)年、自身の今町出立50年を記念して、今町に教育費千円、同じく先祖の地・西野にも千円を寄附しました。
1938(昭和13)年、今町を中心とする雲壮会、入澤内科同窓会、友人、門人たちが、郷里今町の誕生の地に胸像を建設、除幕式を行いました。祝賀会には達吉、家族らも参加して盛大に祝いました。
祝賀会ののち、達吉は赤倉の迦羅山壮で静養中、体調を崩し、急ぎ帰京。東大呉内科に入院しましたが、療養の甲斐なく亡くなりました。享年74歳でした。
1873(明治6)年(9歳)、父が勤務中に脳溢血で亡くなると、12歳の時、東京の叔父・池田(いけだ)謙(けん)斎(さい)(日本最初の医学博士)の勧めもあり上京。母子ともに池田邸に寄宿し、私塾(漢学)に通いました。漢詩の素養はその時身に付けたものと思われます。
1877(明治10)年(13歳)、東京大学予科に入学。本科へと進みひたすら勉学にはげみ、卒業後はベルツ博士の無給助手として学内に勤務しました。
1890(明治23)年(26歳)、叔父の援助もありドイツに自費留学し、ストラブルヒ大学に入学。のちベルリン大学に移り、1894(明治27)年(30歳)に帰国。
すぐさま宮内省侍(じ)医局(いきょく)勤務、東宮殿下(のちの大正天皇)付を命ぜられました。1895(明治28)年、東京帝国大学助教授に、1901(明治34)年には同教授に就任。翌年、恩師ベルツ博士の退任の後を受け、大学内で入澤内科を開設しました。
1912(明治45)年に欧州視察を命ぜられ、欧州、米国の医学の実情を2年間にわたり視察し帰国。1920(大正9)年には、大正天皇侍医頭(じいかしら)の御用を命ぜられました。
1926(昭和元)年、自身の今町出立50年を記念して、今町に教育費千円、同じく先祖の地・西野にも千円を寄附しました。
1938(昭和13)年、今町を中心とする雲壮会、入澤内科同窓会、友人、門人たちが、郷里今町の誕生の地に胸像を建設、除幕式を行いました。祝賀会には達吉、家族らも参加して盛大に祝いました。
祝賀会ののち、達吉は赤倉の迦羅山壮で静養中、体調を崩し、急ぎ帰京。東大呉内科に入院しましたが、療養の甲斐なく亡くなりました。享年74歳でした。