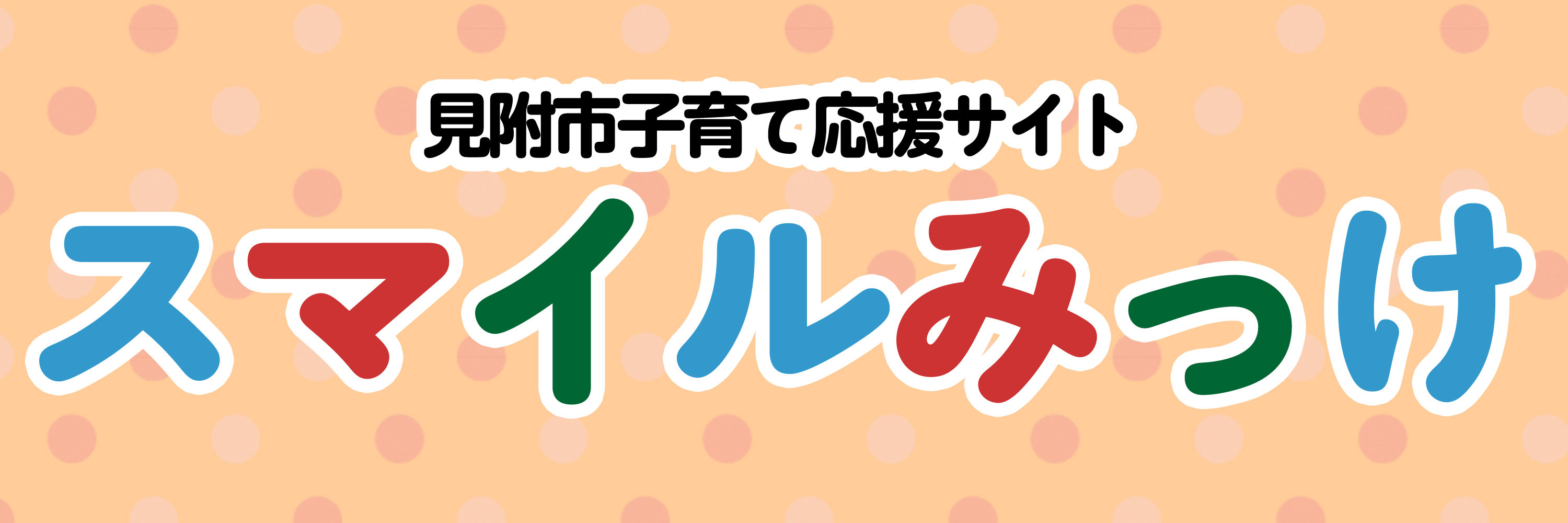本文
18 諏方神社・天満宮・水落蟠龍碑



■諏方神社
諏方神社の祭神は建御名方命(たけみなかたのみこと)。由緒、創立年月日は不祥ですが、まだ今町が羽賀新田と呼ばれていた時代から、産土神(うぶすなのかみ)として崇拝されてきました。
1872(明治5)年、第6大区小6区の村社になりましたが、1880(明治13)年に焼失、同年9月に再建されました。1957(昭和32)年、国道バイバス工事のため、今町大橋下から現在地に移転しました。
境内社として天満宮、住吉神社がありましたが、現在住吉神社は合社されています。
奉額「諏方神社」は東征大総督・有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと)親王の筆によるものです。拝殿には森山信谷、山宮梅園の画、中村不折の書などが奉納されています。
■天満宮
菅原道真公を祀る天満宮の創建については、1477(文明9)年までさかのぼりますが、1895(明治28)年に諏方神社に遷座して今に至っています。
今町は昔から学問、特に子どもの教育には熱心で、天神講(2月25日)には、床の間に道真公の掛け軸を掛け、松竹梅を活け、粉菓子・精進寿司等を供え、その前で子どもたちは素読や習字をする風習がありました。
この天満宮は、いつしか「手習い天満宮」と呼ばれるようになりました。
■水落蟠龍碑
水落蟠龍(1813(文化10)年~1879(明治12)年)は、酒造業兼麻の仲買商として財を成した水落家に生まれ、本名・隆信、幼名・寿作、号を蟠龍と称していました。幼い頃から利発で、12~13歳にして四書五経をそらんじていたと言われています。
1828(文政11)年の三条地震で家を失いましたが、家の再建時に廃業して「蟠龍塾」と名付けた私塾を開き、近郷近在の子弟の教育に力を注ぎました。
門下生の中には大正天皇の侍医頭(じいかしら)を務めた入澤達吉(→「06」参照)がいるほか、多くの人材を世に送り出し、後に今町小学校の初代校長を務めました。
こうした功績を称え、蟠龍の没後、門下生や今町有志により、今町諏方神社境内に顕彰碑が建立されました。
諏方神社の祭神は建御名方命(たけみなかたのみこと)。由緒、創立年月日は不祥ですが、まだ今町が羽賀新田と呼ばれていた時代から、産土神(うぶすなのかみ)として崇拝されてきました。
1872(明治5)年、第6大区小6区の村社になりましたが、1880(明治13)年に焼失、同年9月に再建されました。1957(昭和32)年、国道バイバス工事のため、今町大橋下から現在地に移転しました。
境内社として天満宮、住吉神社がありましたが、現在住吉神社は合社されています。
奉額「諏方神社」は東征大総督・有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと)親王の筆によるものです。拝殿には森山信谷、山宮梅園の画、中村不折の書などが奉納されています。
■天満宮
菅原道真公を祀る天満宮の創建については、1477(文明9)年までさかのぼりますが、1895(明治28)年に諏方神社に遷座して今に至っています。
今町は昔から学問、特に子どもの教育には熱心で、天神講(2月25日)には、床の間に道真公の掛け軸を掛け、松竹梅を活け、粉菓子・精進寿司等を供え、その前で子どもたちは素読や習字をする風習がありました。
この天満宮は、いつしか「手習い天満宮」と呼ばれるようになりました。
■水落蟠龍碑
水落蟠龍(1813(文化10)年~1879(明治12)年)は、酒造業兼麻の仲買商として財を成した水落家に生まれ、本名・隆信、幼名・寿作、号を蟠龍と称していました。幼い頃から利発で、12~13歳にして四書五経をそらんじていたと言われています。
1828(文政11)年の三条地震で家を失いましたが、家の再建時に廃業して「蟠龍塾」と名付けた私塾を開き、近郷近在の子弟の教育に力を注ぎました。
門下生の中には大正天皇の侍医頭(じいかしら)を務めた入澤達吉(→「06」参照)がいるほか、多くの人材を世に送り出し、後に今町小学校の初代校長を務めました。
こうした功績を称え、蟠龍の没後、門下生や今町有志により、今町諏方神社境内に顕彰碑が建立されました。