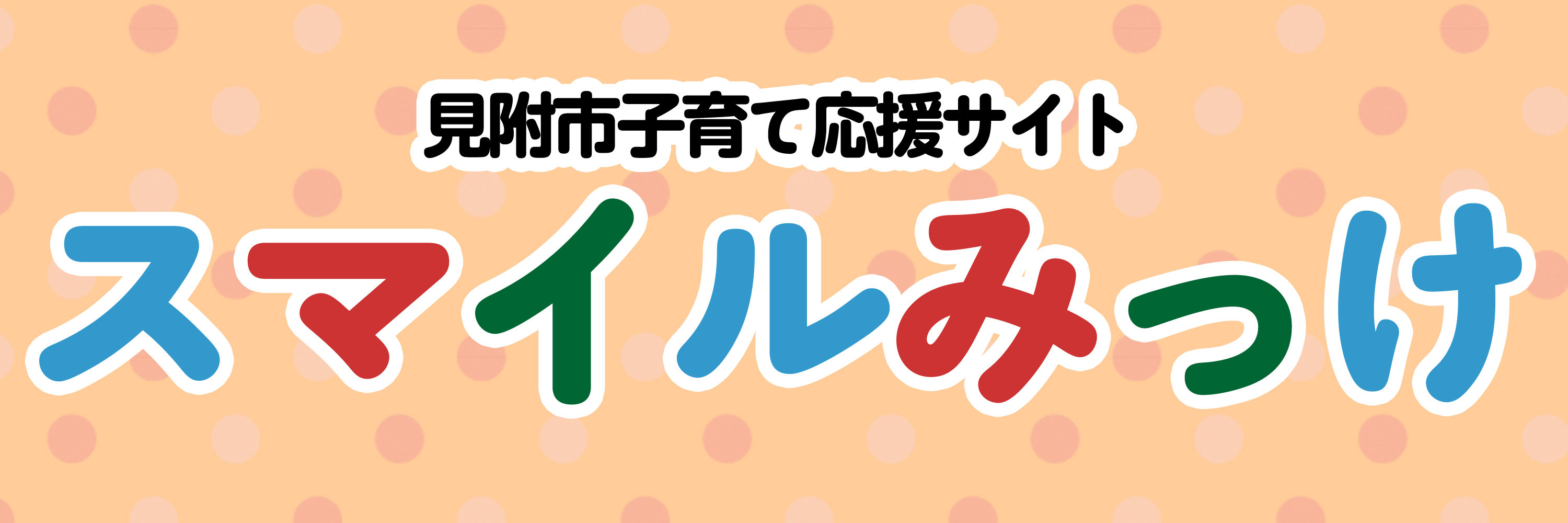本文
20 今町大橋
今町大橋の架橋は古く、1647(正保4)年の「越後国絵図」にすでに記されています。新発田領中之島組の地域は広く、領内の物や人の交流のために早くから橋が架けられていました。刈谷田川は「暴れ川」の異名のとおり、3年に一度くらいに洪水があり、そのたびごとに橋が流され、普請が行われてきました。新発田藩では橋の維持管理に手厚い援助を行い、架け替えの資材は藩が、かかる人夫賃は地元が負担しました。藩は今町に6町7反の橋田を設け、そこから上がる年貢米を積み立て、架け替えの経費に充ててきました。
橋は、昭和4年にトラス式鉄橋に、昭和36年には国道8号線の交通量の増加によってアーチ式に架け替えられました。
現在は、河川改修に伴って位置を変え、「中之島大橋」となっています。
橋は、昭和4年にトラス式鉄橋に、昭和36年には国道8号線の交通量の増加によってアーチ式に架け替えられました。
現在は、河川改修に伴って位置を変え、「中之島大橋」となっています。