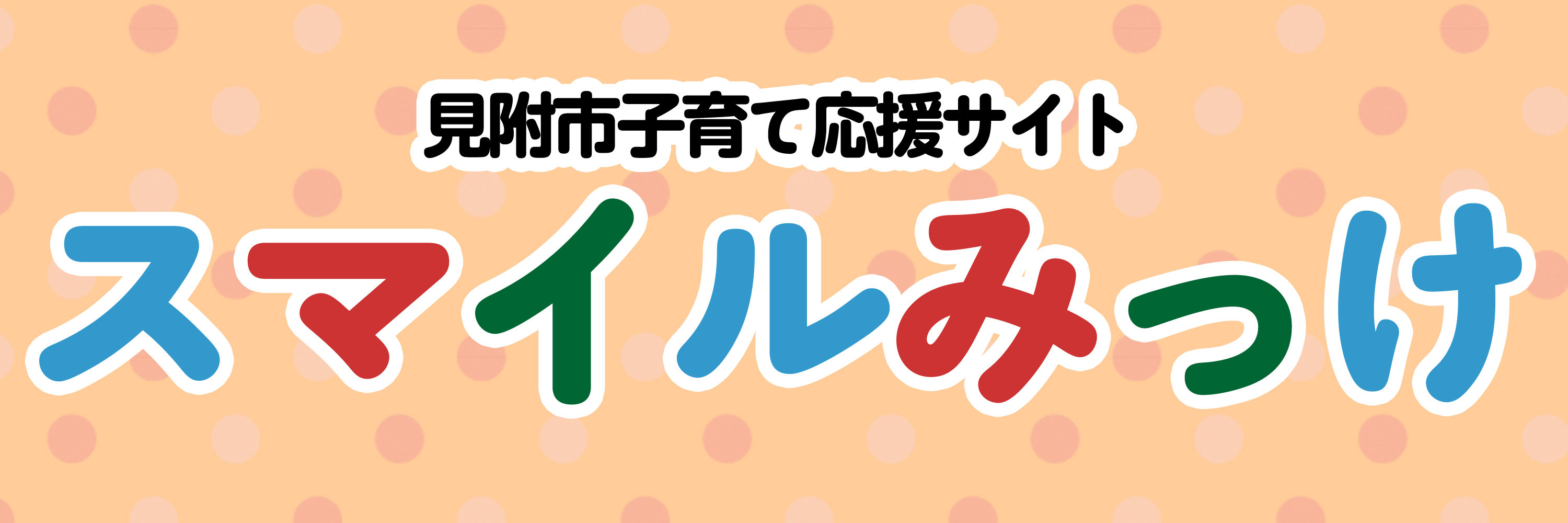本文
固定資産税のよくある質問Q&A
Q1.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がっています。おかしいのではないでしょうか
A.地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる等)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成15年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。(現在は、商業地等の課税標準額の上限は評価額の70パーセントとされています。)
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを訂正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
Q2.4年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなりました。なぜですか
A.新築の住宅に対しては3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)の固定資産税が減額となる措置が設けられております。一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅面積の120平方メートルまでの部分の税額が2分の1に減額されます。したがって、質問のケースの場合、税額が軽減される措置の期間が過ぎたものと思われます。
Q3.家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか
A.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわした、経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。
家屋の建築費は平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価格が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
Q4.年の途中で土地や家屋の売買があった場合、固定資産税はどうなりますか?
A.年の途中で土地や家屋の売買があっても、地方税法の規定により、毎年1月1日現在に登記簿または課税台帳に所有者として登録されている方に対して、その年度分の固定資産税が全額課税されます。
また、固定資産税は年税であるため、月割課税制度はありません。
なお、土地や家屋の売買後の固定資産税の支払いについては、売主と買主との間で契約書等によって取り決めることが行われているようです。
Q5.自分の土地・家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか
A.固定資産税の内容についてお知りになりたい場合は、資産税担当の窓口にお尋ねください。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内までに、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
Q6.納税通知書の内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか
A.納税通知書の内容に疑問がある場合には、資産税担当の窓口にお尋ねください。なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、納付通知書の交付をうけた日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内)となりますのでご注意ください。