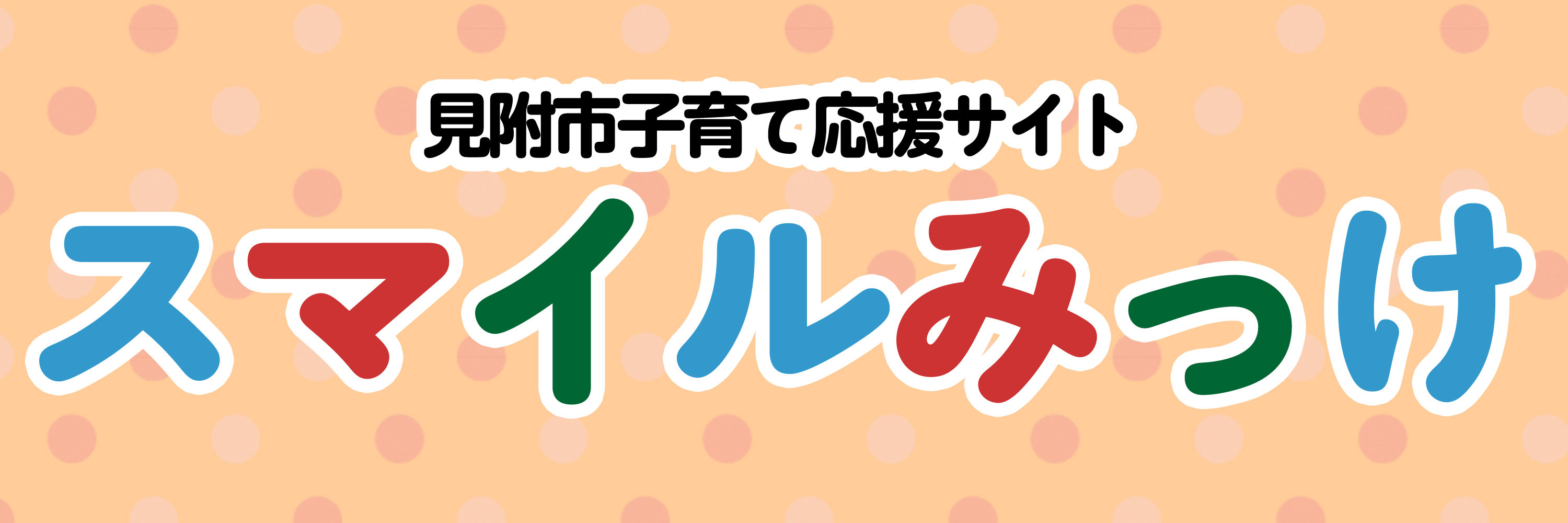本文
税負担の調整措置について
宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。
一方、令和6年度評価替えにおいては、大都市を中心に、地価上昇の結果、負担水準が下落し据置ゾーンを下回る土地が増加するなど、負担水準のばらつきが拡大することが見込まれたことから、そうした土地の負担水準を据置ゾーン内に再び収斂させることに優先的に取り組むべき状況であること等を踏まえ、令和6年度から令和8年度までの負担調整措置については、令和5年度の負担調整措置が継続されることとされています。
「負担水準」とは
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))
税負担が前年度より下がる場合
商業地等の宅地※
負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます)のことをいいます。
住宅用地
負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
税負担が前年度の額に据え置きになる場合
商業地等の宅地
負担水準が0.6以上0.7以下の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
3.税負担が前年度よりもなだらかに上昇する場合
商業地等の宅地
負担水準が0.6未満の土地は、次の計算方法により、なだらかに課税標準額が上昇します。
課税標準額[A]=(新評価額×5%)+前年度課税標準額
[A]が新評価額×60パーセントを上回る場合
課税標準額[A]=新評価額×60パーセント
[A]が新評価額×20パーセントを下回る場合
課税標準額[A]=新評価額×20パーセント
住宅用地
負担水準が1.0未満の土地は、次の計算方法により、なだらかに課税標準額が上昇します。
課税標準額[A]=(新評価額×住宅用地特例率[6分の1または3分の1]×5パーセント)+前年度課税標準額
[A]が新評価額×住宅用地特例率[6分の1または3分の1]×20%を下回る場合
課税標準額[A]=新評価額×住宅用地特例率[6分の1または3分の1]×20パーセント
[A]が新評価額×住宅用地特例率[6分の1または3分の1]を上回る場合
課税標準額[A]=新評価額×住宅用地特例率[6分の1または3分の1]
農地に対する課税
農地は一般農地と市街化区域農地に区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みがとられています。
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。一般農地についても、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率
- 負担水準:0.9~
- 負担調整率:1.025
- 負担水準:0.8~0.9
- 負担調整率:1.050
- 負担水準:0.7~0.8
- 負担調整率:1.075
- 負担水準:~0.7
- 負担調整率:1.100
市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地になります。
市街化区域農地は一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。