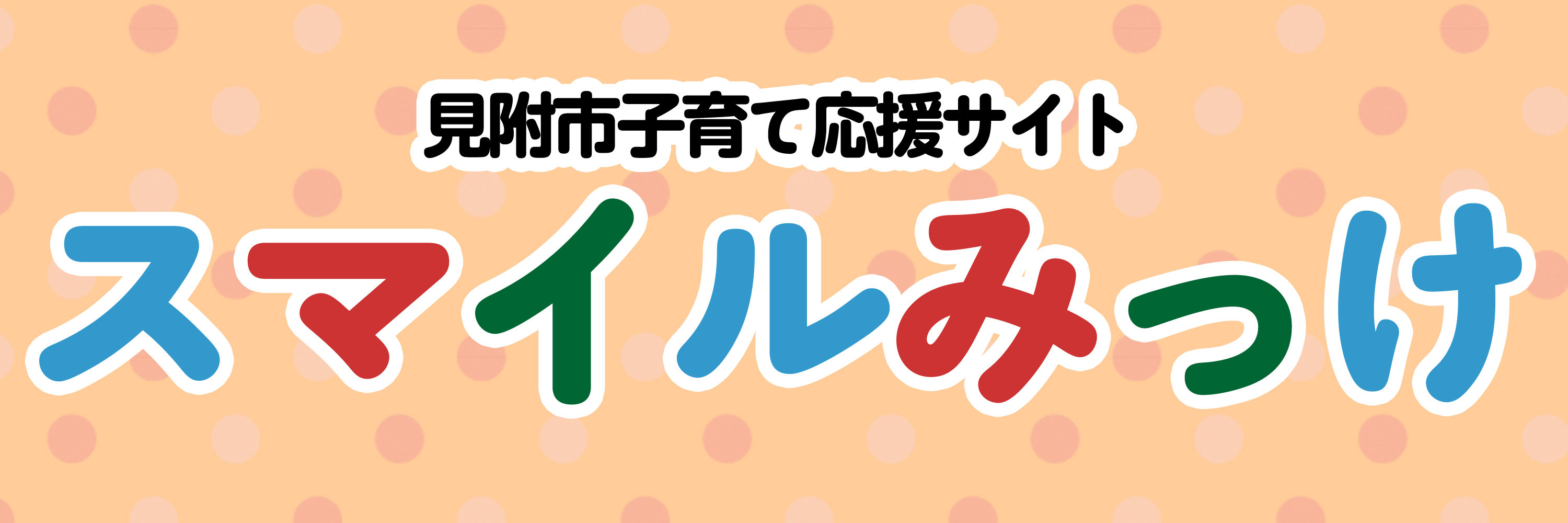-
キーワードで

さがす -
目的別で
さがす -
年齢別で
さがす -
地図で
さがす
本文
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(子宮頸がん予防ワクチン)についてのお知らせ
子宮頸がんとは
子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんです。
日本では毎年、約1.1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約2900人の女性が子宮頸がんで亡くなっています。
また、若い年齢層で発症する割合が比較的高いがんです。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)方も、1年間に約1千人います。
子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因と考えられています。感染は、主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染するといわれています。
子宮頸がんで苦しまないために
(1)HPVウイルスの感染を防ぐためのHPVワクチン予防接種
(2)がん早期発見のための子宮頸がん検診(20歳から2年に1回)が有効です。
子宮頸がん予防ワクチン
子宮頸がんの原因を予防する、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの予防接種について、厚生労働省の勧告に基づき、平成25年6月から積極的な接種勧奨が差し控えられていましたが、国の審議会において、安全性に特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを上回ると認められたことから、令和3年11月、勧奨を再開することが決定されました。
本市においても、国の通知に基づき、下記の対象者へ個別通知を再開するとともに、過去に勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対しても、接種の御案内を送付しています。
対象者
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
接種券・予診票
中学1年生となった女子に接種券・予診票を発送します。
接種方法
- 接種については、見附市個別接種医療機関 [PDFファイル/486KB]へ直接ご予約となります。
- 接種当日は送付された予診票を持参し、医療機関へご提示ください。
接種間隔
ワクチンは3種類あります。一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。
※令和5年4月から、シルガード9も公費で受けられるようになりました。
サーバリックス(2価ワクチン):合計3回接種
1回目 初回接種
2回目 初回接種から1か月以上あける
3回目 初回接種から6か月以上あける
ガーダシル(4価ワクチン):合計3回接種
1回目 初回接種
2回目 初回接種から2か月以上あける
3回目 初回接種から6か月以上あける
シルガード9(9価ワクチン)
1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合:合計2回接種
1回目 初回接種
2回目 初回接種から少なくとも5か月以上あける
※1回目と2回目の接種間隔が5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
1回目の接種を15歳になってから受ける場合:合計3回接種
1回目 初回接種
2回目 初回接種から2か月以上あける
3回目 初回接種から6か月以上あける
有効性とリスク
接種を希望される場合は、ワクチンの有効性と接種によるリスクを十分に理解したうえで接種してください。
子宮頸がんワクチンの安全性や有効性については厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
子宮頸がん予防ワクチン後に症状が生じた方に対する相談窓口
新潟県では、子宮頸がん予防ワクチン接種を受けた後に体調が悪くなった方からの相談窓口を設置しています。お心あたりのある方はご相談ください。
連絡先電話番号
接種後の痛みなどの診療について
子宮頸がん予防ワクチン接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状を呈する患者に対して、より身近な地域において適切な診療を提供するため、都道府県単位で協力医療機関を選定し、協力医療機関、地域の医療機関、厚生労働科学研究事業研究班の所属の専門医療機関(*注)等が連携する診療体制を整備することとなりました。
新潟県の協力医療機関
新潟大学医歯学総合病院(窓口診療科:産科婦人科)
電話:025-227-0374(地域保健医療推進部紹介予約担当)
(注)厚生労働省慢性の痛み対策研究事業の「慢性の痛み診療の基盤となる情報の集約とより高度な診療のための医療システム構築に関する研究班(痛みセンター連絡協議会)」及び「難治性神経因性疼痛の基礎疾患の解明と診断・治療精度を向上させるための研究班」に所属する子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後の痛みの診療を行っている医療機関です。
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関等(厚生労働省)<外部リンク>
医療、救済などに関すること
新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課 電話025-280-5378
学校生活に関すること
新潟県教育庁保健体育課 電話025-280-5622
開設時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
関連リンク
-
新潟県ホームページ