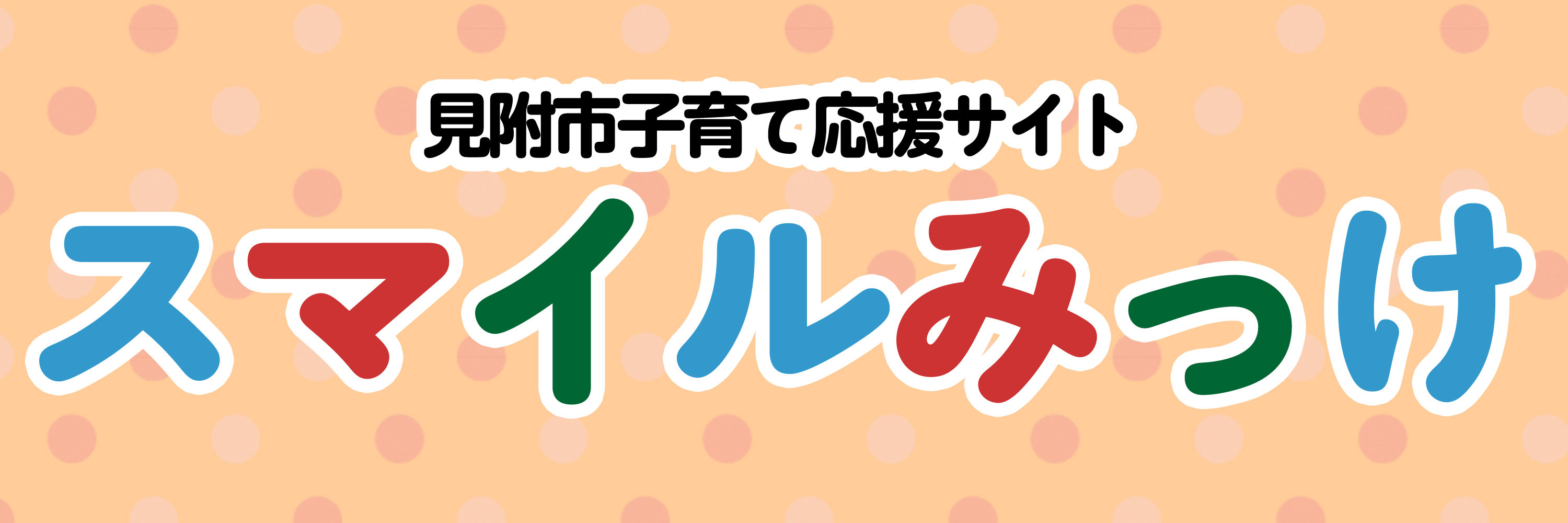ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
-
キーワードで

さがす -
目的別で
さがす -
年齢別で
さがす -
地図で
さがす
本文
未熟児養育医療給付制度のご案内
発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんの入院養育に必要な医療費の一部を助成する制度です。
給付の対象者
見附市にお住まいの1歳未満の乳児であって、出生時に次のような症状があり、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた方が対象です。
該当するかは、主治医に確認してください。
※指定養育医療機関とは県知事等の指定を受けた医療機関です。
新潟県HP 未熟児養育医療給付制度のページへ<外部リンク>
1.出生時体重が2,000グラム以下のもの
2.生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア.一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
イ.体温が摂氏34度以下のもの
ウ.呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
エ.消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔(おう)吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
オ.黄疸(だん) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸(だん)のあるもの
申請手続き
主治医から「養育医療意見書」をもらったら、速やかに手続きをしてください。
申請窓口は、見附市教育委員会こども課(見附市役所4階)です。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書 [PDFファイル/71KB]
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入したもの)
- 世帯調書(表・裏) [PDFファイル/142KB]
- 同意書兼委任状 [PDFファイル/89KB]
- 乳児の加入医療保険が分かる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ等の写し)
- 申請者・世帯構成員・扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 申請者の本人確認のため運転免許証など顔写真のある証明書
※双子の場合、3・4の書類は1枚で結構です。
※1・3・4の書類はこども課窓口にもあります。
申請手続きから医療費の支払いまでの流れ
- 必要な書類をそろえて申請窓口に提出してください。
- 申請内容を審査し、養育医療給付の可否を決定します。
- 給付を決定した場合は、2週間程度で「養育医療券」を郵送しますので、速やかに医療機関に提示してください。
- 保険診療外の費用は、医療機関に支払ってください。
- 入院した月の翌々月以降に、こども課から自己負担金の請求をします。「納入通知書」を郵送しますので、納期限までに必ず見附市役所または金融機関(第四北越銀行・大光銀行・長岡信用金庫・三条信用金庫・新潟縣信用組合・はばたき信用組合・えちご中越農業協同組合・新潟県労働金庫)で納入してください。
医療費について
保険診療分の医療費(食事療養費を含む)が対象となります。
入院した月の翌々月以降に、医療機関から市に医療費の請求があり、市が全額を支払います。その後、こども課から保護者の方に自己負担金の請求をしますので必ず納入してください。
※保険診療外の費用は、別途、医療機関から請求があります。
自己負担金について
乳児と同一世帯の扶養義務者の住民税額等に応じて、徴収基準額(月額)を決定します。
申請月が4~6月の場合は、前年度の住民税額をもとに算定します。
申請月が7~3月の場合は、当年度の住民税額をもとに算定します。
詳細につきましては、下記「見附市未熟児養育医療給付制度のご案内」に掲載している「養育医療措置費負担金徴収基準額表」等を参照してください。
その他
- 転居等により世帯構成が変更した場合は、徴収基準額(月額)も変更になることがあります。こども課まで連絡してください。連絡があった翌月から新しい徴収基準額(月額)を適用します。
- 「出生連絡票」(母子手帳裏のはがき)を必ず出してください。助産師が無料で家庭訪問に伺います。
- 担当の保健師がお子さんの健康状態の確認のため連絡させていただく場合があります。
その他詳細については、見附市未熟児養育医療給付制度のご案内をご覧ください。
見附市未熟児養育医療給付制度のご案内 [PDFファイル/452KB]