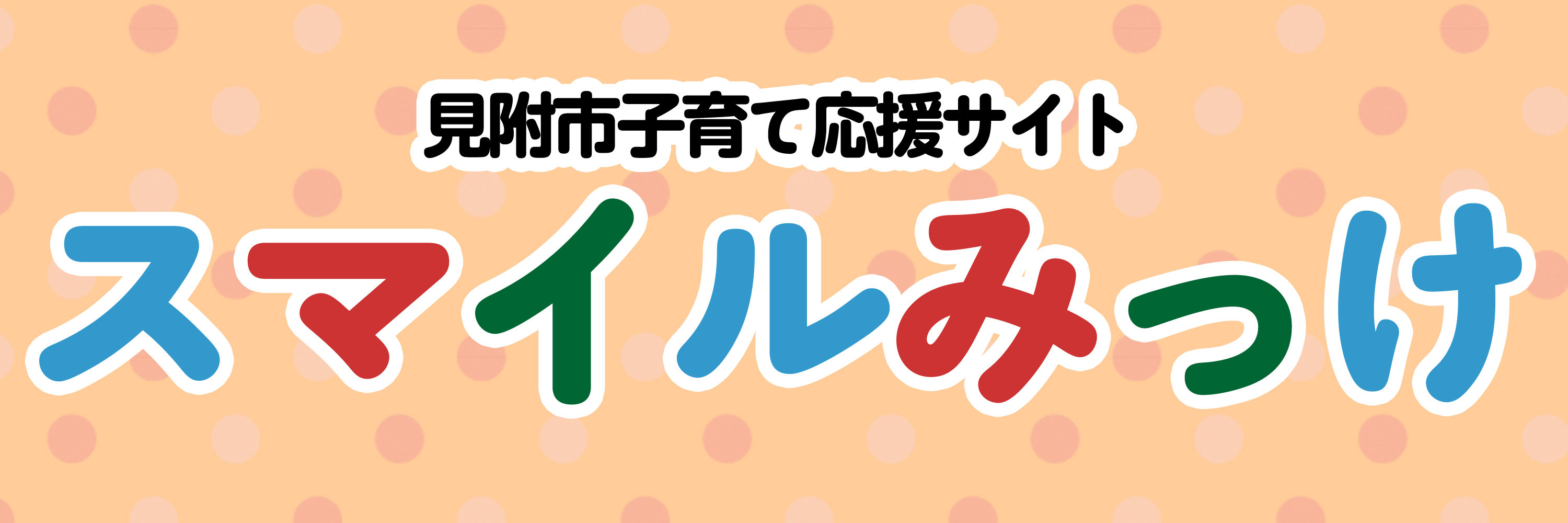本文
出産育児一時金の支給
令和5年4月1日から、下記のとおり支給額が変わりました。
国民健康保険に加入されている方が出産すると、申出により出産育児一時金として出産児1人につき50万円(または48万8千円※)が支給されます。流産・死産でも妊娠12週以上(85日以上)であれば支給されます。
また、会社を退職後6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から受け取ることができます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限る。)その際に直接支払制度を利用する場合は、退職時に交付される「資格喪失証明書」が必要です。
※公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩した場合と22週未満の出産(流産等を含む)の場合は48万8千円の支給となります。
出産育児一時金の医療機関への直接支払制度について
お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、平成21年10月から、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として国保から直接医療機関に出産育児一時金を支払う仕組みへと変更になっています。
ただし、直接、医療機関に出産育児一時金が支払われることを望まれない方は、出産後に国保に申請し受け取ることも可能です。(その場合、現金で医療機関にお支払いいただくことになります。)
手続きの流れ
- 出産される病院で保険証を提示し、直接支払制度を活用する旨の合意文書を取り交わしてください(直接支払制度を活用しない場合は、その際にも直接支払制度を活用しない旨の合意文書を取り交わすようになります)。
- 分娩費用が出産育児一時金の額(50万円または48万8千円)を超える場合は超えた金額が医療機関から請求されます。分娩費用が出産育児一時金の額未満の場合は差し引いた金額を国保からお支払いしますので下記のとおり支給申請をしてください。
分娩費用が出産育児一時金の額未満で国保に残額支給請求をする場合、出産育児一時金の医療機関への直接支払制度を利用しない場合
出産後、下記のものをお持ちいただき、支給申請をしてください。
- 医師又は助産師が発行した出生証明書等、出産を証明する書類。
- 医療機関から交付される「出産育児一時金の医療機関への直接支払制度」を利用する(または利用しない)旨の合意文書の写し
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
- 窓口に来られる方の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
- マイナンバーのわかるもの(世帯主と出産した方のもの)
- 世帯主名義の口座情報のわかるもの
※世帯主以外の口座へ振込む場合はその通帳と世帯主の認印をお持ちください。
※通帳 または 通帳のコピー(見返し面など金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)が記載してあるページ)をお持ちください。
デジタル通帳などで紙の通帳が発行されていない場合は、通帳イメージを印刷したものをお持ちください。(詳しい印刷方法などは各金融機関へお問い合わせください。)
申請場所
- 健康福祉課 国民健康保険係(見附市保健福祉センター内)