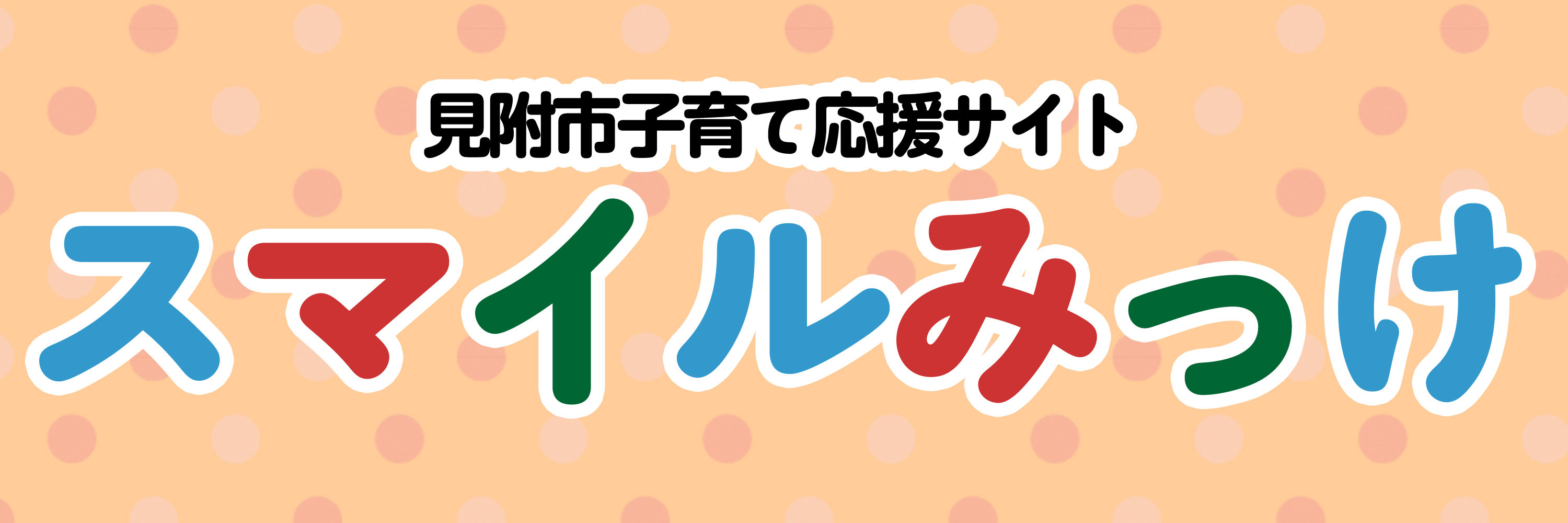本文
コンビニで住民票の写し等各種証明書が取得できます
コンビニで住民票の写し等が取得できます
マイナンバーカードを使って、全国の主なコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から住民票の写しなどの証明書を取得することができます(コンビニ交付)。
※コンビニ交付にはマイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」機能が必要です。利用者証明用電子証明書機能がついていない方は、市民税務課の窓口で機能を付けることができますので、マイナンバーカードを持って市民税務課マイナンバー窓口までお越しください。
発行可能な証明書
住民票の写し
- 取得できる人:見附市に住民登録をしている人
- 取得できる範囲:本人又は同一世帯の人
- 手数料(1通):300円
- 注意事項:除票は除く、世帯主名及び続柄の表示の有無を選択可、本籍地及び筆頭者氏名の表示の有無を選択可
印鑑登録証明書
- 取得できる人:見附市に住民登録をしている人
- 取得できる範囲:本人
- 手数料(1通):300円
戸籍証明書(現在戸籍の全部・個人事項証明書)
- 取得できる人:見附市に本籍がある人(見附市に住民登録がない人は利用登録申請が必要)
- 取得できる範囲:本人又は同一戸籍の人
- 手数料(1通):450円
- 注意事項:除籍、改製原戸籍は除く
戸籍の附票の写し(現在戸籍)
- 取得できる人:見附市に本籍がある人(見附市に住民登録がない人は利用登録申請が必要)
- 取得できる範囲:本人又は同一戸籍の人
- 手数料(1通):300円
所得証明書、所得・課税証明書
- 取得できる人:その年の1月1日時点で見附市に住民登録のある人
- 取得できる範囲:本人
- 手数料(1通):300円
- 注意事項:最新年度のみ取得可。1月1日時点で本市に住民登録があっても、現在の住民登録地が市外であれば、コンビニエンスストアで見附市の各種税証明は取得不可。
所得・課税証明書への定額減税額の記載について
- 所得・課税証明書に個人住民税の定額減税額や定額減税前の住民税所得割額等の記載を希望する方は、市民税務課窓口または今町出張所で取得してください。
- コンビニ交付では、定額減税後の税額表記となり、定額減税に関する記載はありません。定額減税に関する記載が必要か、事前に提出先にご確認ください。
- コンビニ交付で所得・課税証明書を発行後に、定額減税に関する記載が必要だと判明した場合は、市民税務課窓口(0258-62-1700)へご相談ください。
-
定額減税の詳細は令和6年度個人住民税の定額減税についてをご覧ください。
※コンビニで発行する住民票の写しには、住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載はありません。
※市役所窓口で印鑑登録証明書を発行する場合には、今まで通り印鑑登録証が必要になります。
- 転入・転居や婚姻などの異動をした場合、証明書に反映されるまでに1週間程度の日数を要します。詳しくはお問い合わせください。
- 見附市外に住民登録されていて、見附市に本籍がある人も、マイナンバー(個人番号)カードを使って戸籍証明書・戸籍の附票の写しを取得することができます。ただし、利用するには事前に利用登録申請が必要となります。詳しくは「戸籍証明書・戸籍の附表の写しのコンビニ交付サービス(見附市外在住者向け)」をご覧ください。(※見附市に住民登録があり、かつ、見附市に本籍地がある人の場合は、利用登録申請の必要はありません。)
- 見附市役所、今町出張所でも今までどおり証明書を発行しています。
ご利用可能な主な店舗
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンリテール
※キオスク端末(マルチコピー機)の設置店舗に限ります。
利用の流れ(例:世帯全員の住民票の写しを取得する場合)
- 各コンビニのキオスク端末(マルチコピー機)のメニュー画面から「行政サービス」を選択
- 証明書交付サービス(コンビニ交付)を選択
- マイナンバー(個人番号)カードを所定の場所に置く
- マイナンバー(個人番号)カードを取り外す
- 「お住まいの市区町村の証明書」を選択
- 4ケタの暗証番号を入力
- 必要な証明書を選択(例:住民票の写しを選択)
- 交付種別を選択(例:世帯全員を選択)
- 証明書の記載項目を選択 世帯主・続柄の記載 本籍地・筆頭者の記載の有無
- 必要な部数を入力
- 発行内容を確認
- お金を入れてプリントスタート
- プリントされた証明を受取り
- 忘れ物の確認 (マイナンバー(個人番号)カード、おつり、領収書など)
- 取引を終了
※各店舗によって利用の流れが異なる場合があります。
各コンビニの取得方法については証明書の取得方法<外部リンク>をご覧ください。
利用可能な時間帯
午前6時30分~午後11時(ただし、年末年始の12月29日から1月3日と年に数回、メンテナンスのためご利用できないことがあります。)
※メンテナンスの時期につきましては、別ページをご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 15歳未満の方、成年被後見人の方は、ご利用できません。
- コンビニで発行した証明書代の返金、交換はできませんので、ご注意ください。
- 一通あたり複数枚にわたる証明書の場合、ホチキス留めがされません。ページ番号と固有番号が印刷されますので、確認の上取り忘れのないようにお願いします。なお、分けて使用することはできませんのでご注意ください。おつりの取り忘れにご注意ください。
- マイナンバー(個人番号)カードの交付当日は利用できません。翌日からの利用になります。
- マイナンバー(個人番号)カードを保有していても、転入・転出等の届け出の際に継続利用の手続きをされていない場合は利用できません。
- 転入・転出等の届け出の際に継続利用手続きをした場合、翌日からの利用になります。
- マイナンバー(個人番号)カードを保有していても、利用者用電子証明書が搭載されていない、あるいは、有効期限経過後に更新手続きをしていない場合は利用できません。
- 入力する暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかります。ロック解除のためには本人もしくは法定代理人が、マイナンバー(個人番号)カードと本人確認書類(免許証等)と印鑑を市役所のマイナンバー窓口まで持参し、暗証番号の初期化を行う必要があります。
- キオスク端末(マルチコピー機)では特殊な印刷を行いますので証明書が印刷されるまで数分かかる場合があります。印刷が完了するまでキオスク端末(マルチコピー機)の前から離れないようにしてください。
セキュリティ対策について
- マイナンバー(個人番号)カード内のICチップの情報とご自身が設定した暗証番号を照合して本人確認を行います。
- 画面操作、支払、交付まで一貫してキオスク端末(マルチコピー機)を使って行うため、他人の目に触れることなく手続きができることにより個人情報を保護します。また、証明書が印刷された後、画面や音声、アラームなどでマイナンバー(個人番号)カードや証明書の取り忘れ防止対策を実施しています。
- 市と店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)との間のデータ通信は、行政用専用回線を使い、データを暗号化して行います。また、証明書を発行した後、データは即座に消去される仕様になっています。
- 印刷された証明書の両面には不正防止処理が施されており、コピーすると「複写」の文字が浮かぶようになっています。
- 証明書裏面中央には証明書情報を暗号化した「スクランブル画像」が印刷されています。問い合わせ専用サイトを通じて証明書の偽変造・改ざんがされていないかチェックすることができます。
詳しくは地方公共団体情報システム機構のコンビニ交付ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ
見附市役所:62-1700
マイナンバーに関するお問い合わせ
- 市民税務課 マイナンバー窓口:内線147
証明書に関するお問い合わせ
- 市民税務課 市民窓口係:内線144
- 市民税務課 管理税収係:内線128