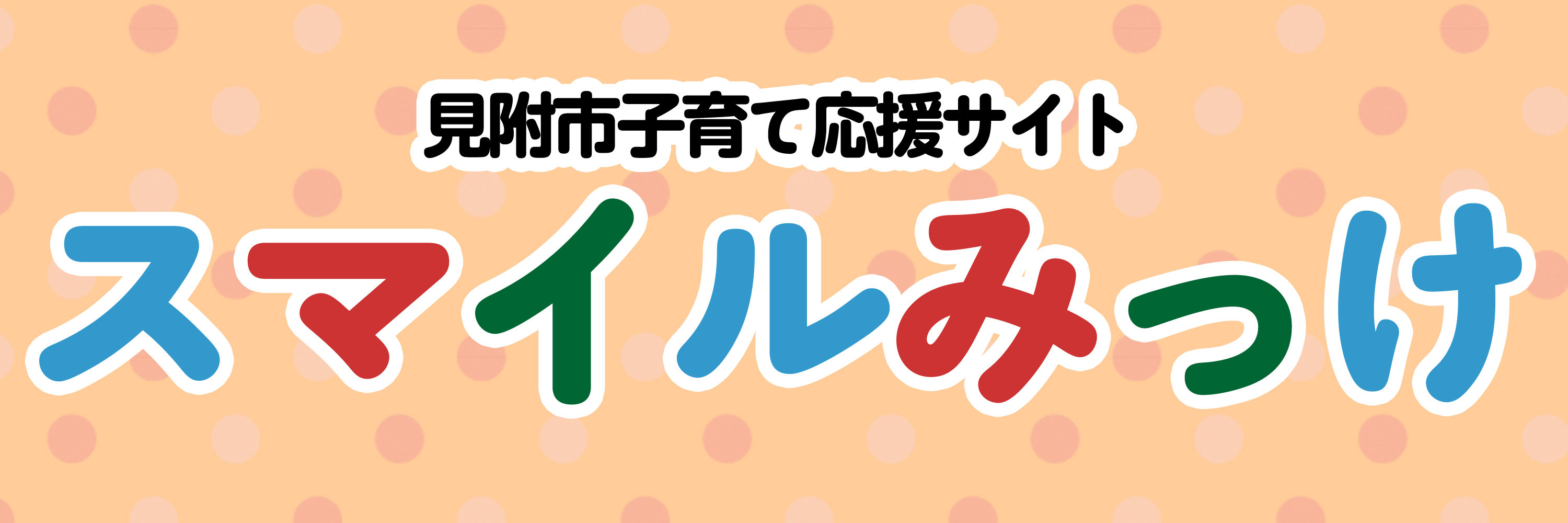本文
【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金(不足額給付分))
本給付金の申請は令和7年12月17日(水曜日)で受付を終了しました。
調整給付金(不足額給付分)とは
調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
調整給付金(不足額給付)の対象者へは7月下旬から順次、通知書を送付しました。
調整給付金(不足額給付)については個々の所得・課税状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。
不足額給付の対象者(1)
以下の1~3のすべてに該当する方
- 令和7年1月1日時点で見附市に住民登録があること(住登外課税者を含む)
- 合計所得金額が1,805万円以下であること
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(給付不足額)が生じること
給付の対象となりうる方の例
- 退職などにより、令和5年中の所得に比べて令和6年中の所得が少なくなった方
- 子どもの出生などにより、令和6年分から扶養親族が増えた方
- 当初調整給付後の申告などにより、令和6年度個人住民税所得割額が少なくなった方
支給額
所得税、個人住民税所得割それぞれに控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から、当初調整給付額を差し引いた金額
※不足額給付時における令和6年分所得税額は、令和7年度個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出します。そのため、実際の所得税額とは若干誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算出するため、給付額への影響はほとんどありません。万が一給付額に影響があると思われる場合は、市民税務課民税係へご連絡ください。
不足額給付の対象者(2)
以下の1~5のすべてに該当する方
- 令和7年1月1日時点で見附市に住民登録があること(住登外課税者を含む)
- 合計所得金額が1,805万円以下であること
- 令和6年度所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること(本人が定額減税の対象外)
- 税制度上、扶養親族の対象外であること(扶養親族としても定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付(注)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと
(注)低所得世帯向け給付とは以下の給付金を指します。
- 令和5年度個人住民税非課税(または均等割のみ課税)世帯への給付金(7万円・10万円)
- 令和6年度新たに個人住民税非課税(または均等割のみ課税)となる世帯への給付(10万円)
給付の対象となりうる方の例
- 所得割課税世帯に属する専従者の方
- 合計所得金額が48万円超であり、令和6年分所得税および個人住民税所得割額が0円の方
支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円
申請方法・支給
支給対象となる方には令和7年7月下旬から順次、案内文書を送付しました。
※令和6年中に見附市に転入した方は、見附市から当初調整給付算定自治体(転入前自治体)に対して給付に係る調査を行うため、案内文書の送付が遅くなる場合があります。
よくあるご質問
不足額給付では、申請しないともらえない場合があるのでしょうか?
見附市では、令和6年中に転入した方については、当初調整給付算定自治体(転入前自治体)に対して給付に係る調査を行い、対象者へは見附市から案内文書を送付しました。
令和7年1月2日以降に見附市に転入した場合は不足額給付はどうなりますか?
見附市から不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点でお住まいだった自治体(令和7年度個人住民税を課税している自治体)が不足額給付の算定を行います。
令和6年中に国外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれなかった場合、不足額給付の対象となりますか?
令和7年1月1日時点で見附市にお住まいの方であれば、不足額給付の対象となります。
ただしこの場合、個人住民税の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
不足額給付の案内文書の宛名になっている親族が死亡した場合どうなりますか?
給付金の給付にあたっては、給付対象者本人が「受け取る」旨の意思表示をする必要があります。
「支給のお知らせ」が届いた方
- 「支給のお知らせ」に記載の申出期限までに受給口座の変更手続きを行った後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できる場合があります。
- 申出期限までに上記の手続きをせずに亡くなられた場合は受給できません。
「支給確認書」が届いた方
- 申請前に亡くなられている場合は受給できません。
- 申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できる場合があります。その場合は、振込先口座の変更手続きなどがありますので、見附市市民税務課民税係までご連絡ください。
令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか?
不足額給付の対象にはなりません。
令和6年分の所得税の計算における扶養の状況は、令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。
令和6年に実施された当初調整給付金を受給していなくても、不足額給付を受給することはできますか?
不足額給付の対象要件を満たしていれば、令和6年の当初調整給付金の対象外であった方も不足額給付を受給できます。
ただし、当初調整給付の受給対象であった方が、申請忘れ等により受給されなかった場合、不足額給付の給付時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
修正申告などを行った結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合はどうなりますか?
修正申告等により、基準日以降に定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)としても、不足額給付額の再算定はできません。
※不足額給付は案内文書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で受給してください。
長期出張などにより、現在住民登録地に居住していないため、不足額給付の手続きができません。どうしたらいいですか?
不足額給付に関する書類の送付先を住民登録地以外に変更する場合、「送付先変更届」の提出が必要です。届出の方法については、見附市市民税務課民税係にお問い合わせください。
※送付先は国内に限ります。
給付金を装った詐欺にご注意ください
市が以下のようなことを行うことはありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作を求めること
- 給付にあたり、手数料の振り込みを求めること
- メールやショートメッセージを送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 訪問により口座情報などの個人情報を確認すること
注意喚起リーフレット(内閣官房) [PDFファイル/490KB]
関連情報
- 令和6年度個人住民税の定額減税について
- 総務省ホームページ(個人住民税の定額減税)<外部リンク>
- 内閣官房ホームページ(新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置)<外部リンク>
- 国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)<外部リンク>